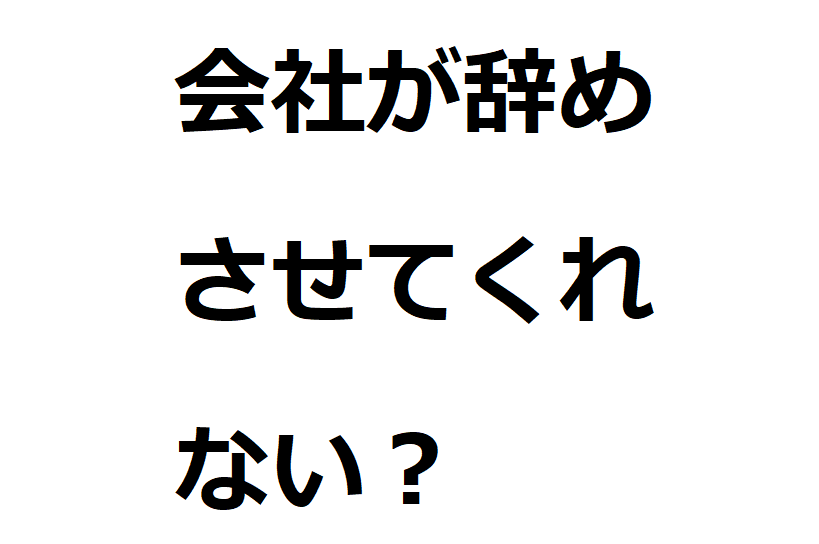働いている会社を辞める場合、上司などに退職届(退職願)を提出して退職の意思表示を行うのが通常ですが、会社側が退職届(退職願)の受け取りを拒否したり、様々な理由を付けて退職を制限し就労を強制するケースが見られます。
しかし、憲法で「奴隷的拘束の禁止(憲法18条)」が明確に保障されている以上、使用者(雇い主)が労働者の退職を制限し就労を強制する行為は到底認められるべきではないとも思えます。
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
では、このように使用者(雇い主)が労働者の退職を拒否し就労を強いる行為に法律上の問題はないのでしょうか?
また、実際に会社から退職を拒否された場合、具体的にどのように対処すれば仕事を辞めることができるのでしょうか?
退職の意思表示をしたにもかかわらず、仕事を辞めさせてもらえない場合の具体的な対処法が問題となります。
使用者(雇い主)が労働者の退職を拒否することは法的に認められない
結論から言うと、使用者(雇い主)が労働者の退職を拒否し就労を強制することは法的に認められていません。
ですから、仮に労働者が退職届(退職願)を提出するなどして退職の意思表示をしたにもかかわらず使用者(雇い主)が労働者の退職を拒否して就労を強制するような場合、その使用者(雇い主)には法律違反として民事上のペナルティ(労働者から慰謝料等の損害賠償請求を受けること)または刑事上のペナルティ(犯罪行為として刑事罰を受けること)が発生する余地もあることになります。
このような結論に至る理由は2つあります。
一つは、法律で労働者に「退職の自由」が明確に認められていること。
もう一つは、退職の意思を有する労働者に就労を強制する行為が「強制労働の禁止」を規定した労働基準法5条に抵触することになるからです。
(1)労働者に「退職の自由」が認められていること
労働者が使用者(雇い主)との間で取り交わす雇用契約には、働く期間を「いつからいつまで」というように限定せず定年まで勤めあげることが前提となるいわゆる終身雇用で雇い入れられる「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」と、働く期間が「〇年〇月から〇年〇月まで」というように限定され契約期間が満了した場合は契約の更新が必要となる「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」の2種類に分けることができますが、いずれの雇用契約の場合であっても労働者には法律で「退職の自由」が保障されています。
ア)「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」の場合
労働者と使用者(雇い主)との雇用契約が「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」の場合、労働者は「2週間」の予告期間さえ置いて退職の意思表示を行うことによって「いつでも」「自由に」退職することが法律で認められています(民法627条)。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
そしてこの規定は、雇用契約が労働者の身体の自由を使用者の指揮命令下で拘束する性質があることから、「奴隷的拘束の禁止」を保障した憲法18条の要請上、最大限に保障されるべきものと考えられています。
したがって、この「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」で働く労働者の「退職の自由」を規定した民法627条を制限する当事者間の合意あるいは使用者(雇い主)の行為は違法(無効)と解釈されますから、使用者(雇い主)が労働者の退職を拒否し、退職を申し出た労働者に就労を強制する行為は認められないことになるのです。
イ)「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」の場合
以上は、労働者と使用者(雇い主)との契約が「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」の場合も同じです。
「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」とは、働く期間が「〇年〇月から〇年〇月まで」というように限定され契約期間が満了すれば契約の更新がない限り退職を強制される契約を指しアルバイトやパート、契約社員などいわゆる非正規労働者として雇い入れられる場合がこれに当たりますが、正社員であっても働く期間が「いつからいつまで」というように限定されている場合はこの「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」となりますので注意が必要です。
この「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」で働く労働者は契約期間が満了するまではその使用者(雇い主)の下で働かなければならない雇用契約上の義務を負担していることになりますので、契約期間が満了する「前」は労働者の一存で勝手に退職してしまうと契約違反として債務不履行責任(民法415条)を負担しなければならないのが原則となります。
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
しかし、契約期間が満了すれば雇用契約上の義務はすべて履行したことになりますから、契約期間が満了した時点で労働者に「退職の自由」が認められることになります。
また、仮に契約期間が満了する「前」であっても「やむを得ない事由」があったり「契約期間の初日から1年が経過」した場合には「いつでも」「自由に」退職することが法律(民法628条、労働基準法137条)で認められていますから、このような法律の条件を満たす限り契約期間の途中で退職する労働者に債務不履行責任(民法415条)は発生せず、労働者に「退職の自由」は保障されていると考えられています。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
期間の定めのある労働契約(中略)を締結した労働者(中略)は、(中略)民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
(※注釈:ただし厚労大臣が定める高度な専門的知識を有する労働者や満60歳以上の労働者は適用除外されています)
したがって「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」の場合にも、労働者に「退職の自由」は法律上保障されているということが言えますから、使用者(雇い主)が労働者の退職を拒否して就労を強制するような行為は認められないということになります。
(2)退職の意思を有する労働者に就労を強制する行為は「強制労働の禁止」を規定した労働基準法5条に違反する
以上のように、退職の意思を有する労働者の退職を制限し就労を強制する行為が違法性を帯びる点については、仮にこの「退職の自由」が保障されないケースであっても結論に変わりはありません。
なぜなら、退職の意思を有する労働者に就労を強制することは、たとえそれが「退職の自由」が保障されない労働者であっても、「強制労働の禁止」を規定した労働基準法5条に違反することになるからです。
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
先ほどの(1)で説明した「退職の自由」だけを考えて解釈する場合、「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」で働く労働者が「2週間の予告期間」を「置かずに」退職する場合は民法627条の要件を満たさないで退職することになりますから、もし仮に「2週間の予告期間」を「置かず」に使用者(雇い主)の承諾を得ないで一方的に退職し、それによって使用者(雇い主)に何らかの損害が発生した場合には、その労働者は契約違反としての債務不履行(民法415条)や不法行為(民法709条)に基づく損害賠償責任が発生する余地が生じます。
また「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」においても、「やむを得ない事由」が無く、「契約期間の初日から1年が経過」していないにもかかわらず契約期間の途中で退職する場合には民法628条や労働基準法137条の要件を満たさないで退職することになりますから、もし仮に「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」で働く労働者が「やむを得ない事由」や「契約期間の初日から1年が経過」した事実がないにもかかわらず契約期間が満了する「前」に退職してしまった場合において使用者(雇い主)に何らかの損害が発生した場合には、その労働者は契約違反としての債務不履行(民法415条)や不法行為(民法709条)に基づく損害賠償責任を負担しなければならない余地が生じるでしょう。
しかし、このように労働者が法律や雇用契約に違反して退職してしまう場合のように、労働者に「退職の自由」が保障されない場合であっても、使用者(雇い主)は退職の意思を有する労働者の退職を拒否したり就労を強制させることはできません。
なぜなら、たとえ労働者が法律(民法627条、民法628条、労働基準法137条)の要件を満たさずに一方的に退職する場合であっても「強制労働の禁止」を規定した労働基準法5条の規定は「奴隷的拘束の禁止」を保障した憲法18条の要請上、最大限に保障されなければならないからです。
労働者が法律(民法627条,同628条,労働基準法137条)に違反して退職した場合には労働者に債務不履行責任(民法415条)や不法行為責任(民法709条)が生じることになりますが、使用者(雇い主)はその責任を基にした損害賠償請求権を行使できるだけ、つまりお金を請求できるだけで労働者の身体を拘束し労働を強制することはできないわけです。
したがって、「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」で働く労働者が「2週間の予告期間」を「置かずに」退職する場合であったり、「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」で働く労働者が「やむを得ない事由」がなく「契約期間の初日から1年が経過」していないのに、法律上または雇用契約上の根拠なく一方的に使用者(雇い主)の承諾を得ずに契約期間の途中で退職する場合であっても、使用者(雇い主)はその退職する労働者の退職を拒否して就労を強制することはできないということになるのです。
会社が辞めさせてくれないときの対処法
以上で説明したように、労働者側にどのような法律違反もしくは契約違反行為があったとしても、労働者に「退職の自由」が認められ「強制労働の禁止」が保障されていることから、使用者(雇い主)側が労働者の退職の意思表示を拒絶して労働を強制することは認められません。
ですから、仮に退職届(退職願)を提出するなどして退職の意思表示をしたにもかかわらず会社側が受け取りを拒否したり、何かの理由を付けて退職を認めず就労の継続を要求する場合であっても、そのような使用者(雇い主)側の主張は無視して一方的に退職届(退職願)を提出し、その退職の効果が発生する日(※注1、注2)の翌日以降は退職したものとして出社しないようにすれば問題ありません。
また、退職を拒否されて就労を強制される場合には、先ほども説明したように、その使用者(雇い主)は労働基準法5条(強制労働の禁止)に違反することになりますから、労働基準監督署に労基法違反の申告を行って労基署の対処を求めることも可能です。
なお、この場合の具体的な対処法などは、使用者(雇い主)が労働者の退職を妨害するなどして辞めさせてくれないときの対処法などをそのシチュエーションごとに分けて解説していますので、以下のそれぞれのケースごとのページを参考にしてください。
- 会社から退職届(退職願)の受け取りを拒否されて辞めさせてもらえない場合
→ 退職届の受け取りを拒否して辞めさせてくれない会社を辞める方法 - 会社から「正当な理由がない」という理由で辞めさせてもらえない場合
→ 正当な理由がないと辞めさせないと退職を拒否された場合 - 退職届は「所定の様式しか認めない」と言われて退職を拒否された場合
→ 退職届は会社所定の様式しか認めない…との就業規則は有効か - 「辞めたら損害賠償請求するぞ!」と脅されて会社を辞めさせてもらえない場合
→ 辞めたら損害賠償請求するぞ…と退職を拒否された場合 - 就業規則の「退職には会社の許可が必要」との規定を根拠に辞めさせてくれない場合
→ 退職には会社の許可が必要とする就業規則・誓約書は有効か - 「退職届は〇か月以上前に提出しないと辞めさせない」と言われて退職できない場合
→ 退職届は〇か月前に提出しないと辞めさせないといわれた場合 - 「代わりの人材を紹介しないと辞めさせない」と言われて辞めさせてもらえない場合
→ 代わりの人材を連れてこないと辞めさせないと言われた場合 - 「~まで退職しません」と誓約したことを根拠に辞めさせてくれない場合
→ 「退職しない」旨の誓約書を根拠に会社が辞めさせてくれない場合 - 退職の意思表示をすると上司から監禁や暴行を受ける恐れがある場合
→ 退職届を出すと暴行・監禁される場合でも安全に会社を辞める方法