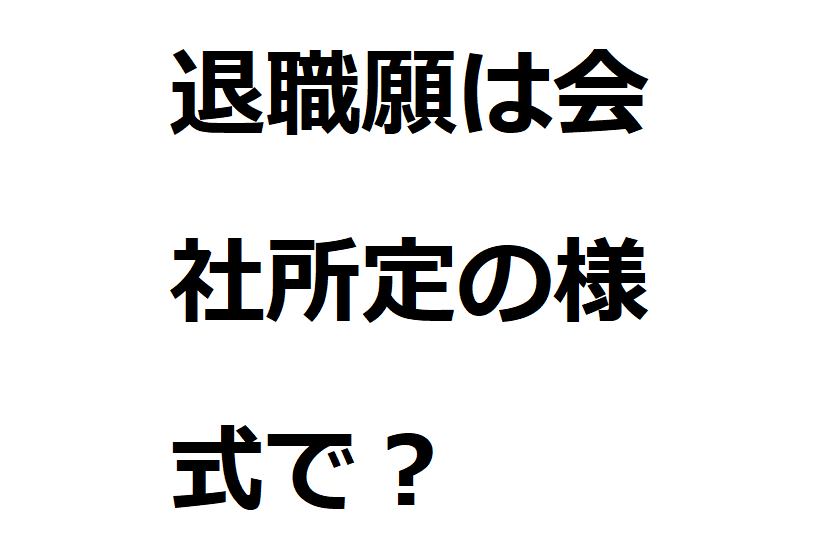勤務先の会社を辞める際は直属の上司などに退職届(退職願)を提出し退職の意思表示を行うのが一般的ですが、会社によっては就業規則などに「退職する際は会社所定の様式で作成した退職届(退職願)を提出しなければならない」などと規定されていることを根拠に、労働者が任意の様式で作成した退職届(退職願)を提出した場合に退職を拒否する事例が見られます。
また、悪質な会社によっては、その就業規則で定められた「所定の様式」を労働者が尋ねても教えず、労働者が事実上、退職届(退職願)を提出することができないようにして退職を妨害しているケースもあるようです。
このような場合、会社所定の様式で作成した退職届(退職願)を提出しなければ会社を辞めることができないのでしょうか?
就業規則等における「退職する際は会社所定の様式で作成した退職届(退職願)を提出しなければならない」とする規程の有効性が問題となります。
退職届(退職願)の様式を限定する就業規則等の規定は「無効」
結論から言うと、就業規則に「退職する際は会社所定の様式で作成した退職届(退職願)を提出しなければならない」などと規定されていたとしても、そのような規定は「無効」と考えて差し支えなく、そのような規定は無視して適宜の様式で作成した退職届(退職願)を提出すれば法律上問題なく退職することが可能です。
なぜなら、労働者には法律で「退職の自由」が保障されており(民法627条,同628条,労働基準法137条)、就業規則等でこれに制限を加えることを認めてしまうと「強制労働の禁止」を規定した労働基準法5条に、ひいては「奴隷的拘束の禁止」を保障した憲法18条に反し不都合な結果となるからです。
(1)「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」の場合
労働者が雇い主に雇われる際に契約期間が「いつからいつまで」というように限定されておらず終身雇用で定年まで勤めあげることが前提となっている場合の雇用契約は「期間の定めのない雇用契約」と呼ばれます。
一般的に正社員のようないわゆる非正規労働者として雇用される場合がこれに当たりますが、アルバイトやパートとして雇い入れられる場合であっても契約期間が「〇年〇月から〇年〇月まで」というように限定されていない場合にはこの「期間の定めのない雇用契約」となるので注意が必要です。
この「期間の定めのない雇用契約」として働く場合において労働者が退職したい場合、退職希望日の2週間前までに退職届(退職願)を提出するなどして退職の意思表示を行えば法律上有効に退職の効果が生じることが法律で保障されています(民法627条1項)。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
ですから、「期間の定めのない雇用契約」で働く労働者が退職する場合には、2週間の予告期間さえ置いておけば退職の意思表示を行うことによって「いつでも」「自由に」退職することが法律上保障されていることになるわけです。
この点、就業規則等で「会社所定の様式」で作成した退職届(退職願)を提出することを義務付けて、会社所定の様式以外の様式で退職の意思表示を申し出た労働者の退職を制限することが認められるかが問題となりますが、この民法627条の規定は労働者の「退職の自由」を保障する規定であり法律学上”強行法規”と考えられていますので、これを労働者にとって不利益となるように変更を加え「退職の自由」を制限することはできないものと考えられています。
なぜなら、このような制限を認めてしまうと「強制労働の禁止」を規定した労働基準法5条が有名無実化してしまうだけでなく、憲法18条の「奴隷的拘束の禁止」も保障することができなくなってしまうからです。
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
そもそも、労働者が使用者(雇い主)に労働力を提供することを約束する「雇用契約(労働契約)」は、労働者が自身の身体の自由を一定の期間その雇い主に提供し雇い主の指揮命令下で拘束されることを意味しますので、憲法18条で保障した「奴隷的拘束の禁止」を侵害しない範囲で必要最小限度に制限される必要があります。
そのために設けられたのが「退職の自由」を保障した民法627条の規定、あるいは「強制労働の禁止」を規定した労働基準法5条になるわけですから、民法627条の「2週間の予告期間さえ置いておけばいつでも自由に退職できる」という「退職の自由」は労働者の不利益に変更することは認められないわけです。
ですから、民法627条で「2週間の予告期間を置いて退職すること」が認められている以上、たとえ就業規則に「退職する際は会社所定の様式で作成した退職届(退職願)を提出しなければならない」などと規定されていたとしても、そのような規定は「無効」と判断して適宜の様式で作成した退職届(退職願)を提出するなどして退職の意思表示を行えば法律上問題なく退職することができるといえるのです。
(2)「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」の場合
以上の理由は「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」の場合も同じです。
「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」とは、働く期間が「〇年〇月から〇年〇月まで」というように限定された雇用契約をいい、アルバイトやパート、契約社員などいわゆる非正規労働者として雇い入れられる場合がこれにあたるのが一般的ですが、正社員として採用された場合であっても働く期間が「いつからいつまで」というように限定されている場合はこの「期間の定めのある雇用契約」となります(※その逆にバイトやパートであっても契約期間が限定されていない場合は前述した(1)の「期間の定めのない雇用契約」となります)。
この「期間の定めのある雇用契約」で働く労働者はその契約期間が満了するまでは退職することが契約上制限されますが、契約期間が満了すれば契約上の違反はありませんので使用者(会社)側の承諾なく一方的に退職することが認められます。
また、仮に契約期間が満了する「前」であっても「やむを得ない事由」がある場合(民法628条)か「契約期間の初日から1年が経過」した場合(労働基準法137条)には、使用者(会社)側の承諾なく「いつでも」「自由に」退職することが法律で認められていますから、「期間の定めのある雇用契約」で働く労働者においても「退職の自由」が保障されているということが言えます。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。(後段省略)。
期間の定めのある労働契約(中略)を締結した労働者(中略)は、(中略)民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
(※注釈:ただし厚労大臣が定める高度な専門的知識を有する労働者や満60歳以上の労働者は適用除外されています)
そして、これらの規定も先ほど説明したのと同じように「強制労働の禁止(労働基準法5条)」や「奴隷的拘束の禁止(憲法18条)」との関係から”強行法規”と解釈されていますから、これらの規定を労働者の不利益に制限することはできないものと考えられます。
したがって「期間の定めのある雇用契約」において、たとえ就業規則に「退職する際は会社所定の様式で作成した退職届(退職願)を提出しなければならない」などと規定されていたとしても、「契約期間が満了」するか「やむを得ない事由」があるか「契約期間の初日から1年が経過」した場合には、そのような規定は「無効」と判断して適宜の様式で作成した退職届(退職願)を提出するなどして退職の意思表示を行えば法律上問題なく退職することができるといえるのです。
退職届(退職願)の様式を制限する規定が「無効」になるのは誓約書にサインしていた場合も同じ
なお、以上は仮に「退職する際は会社所定の様式で作成した退職届(退職願)を提出します」というような誓約書にサインしていた場合であっても同じです。
これまで説明したように「期間の定めのない雇用契約」であっても「期間の定めのある雇用契約」であっても法律で「退職の自由」が認められており、「強制労働の禁止」を規定する労働基準法5条や「奴隷的拘束の禁止」を保障する憲法18条の規定に反して、退職手続きを労働者に不利益に制限を掛けるような当事者間の合意はすべて「無効」と判断されますから、そのような誓約は無効と考えて、適宜の様式で作成した退職届(退職願)を提出しておきさえすれば法律上問題なく退職の効果は発生します。
ちなみに、退職の意思表示は「書面」で行うことは要件とはなっていませんので、口頭で「退職します」というだけでも退職の意思表示としては成立しますから、その意味でも会社所定の様式で作成した退職届(退職願)を提出する必要はないということになります。
使用者が会社所定の様式で作成した退職届(退職願)しか受け付けないとして退職を拒否する場合の対処法
以上のように、たとえ就業規則に「退職する際は会社所定の様式で作成した退職届(退職願)を提出しなければならない」などと規定されていたとしても、法律で労働者に「退職の自由(民法627条,同628条,労働基準法137条)」が保障されており、「強制労働の禁止(労働基準法5条)」や「奴隷的拘束の禁止(憲法18条)」が明確に規定されいますので、そのような会社の主張は無視して適宜の様式で作成した退職届(退職願)を提出するか、あるいは口頭で「退職します」と言って退職しても何ら問題ありません。
もっとも、会社によってはそのような法律の規定を無視して「会社所定の様式」で作成した退職届(退職願)の提出に固執し、適宜の様式で作成した退職届(退職願)の受け取りを拒否して退職を妨害するケースもありますので、そのような場合は以下のような手段を用いて具体的に対処する必要があります。
(1)郵送で退職届(退職願)を送り付ける
会社側が就業規則の規定に固執して会社所定の様式で作成した退職届(退職願)以外の退職届(退職願)の受け取りを拒否するような場合は、適宜の様式で作成した退職届(退職願)を郵送で会社に送り付けて退職の効力が発生した日以降は出社しないようにするのも一つの対処法として有効です。
退職は「退職します」と口頭で通知するか、もしくは退職届(退職願)を提出し、その意思表示が受理権限のある者に到達した時点で有効に成立しますので、仮に退職届(退職願)の受け取りを拒否されたとしても退職の効果は法律上有効に発生することになります。
しかし、後に裁判になった場合に会社側が「退職届(退職願)は受け取っていない」などと反論してきた場合は労働者側で「退職届(退職願)を提出した」ということを立証しなければなりませんから、会社側が退職届(退職願)の受け取りを拒否しているようなケースでは「退職届(退職願)を提出した」という事実の証拠が残らない”手渡し”よりも、客観的な証拠の残る”郵送”で送付しておく方が無難です。
具体的には、提出する退職届(退職願)のコピーを取ったうえで特定記録郵便などで送付しておけば問題ありませんが、将来的に裁判に発展することが確実なケースでは内容証明郵便で退職届(退職願)を送り付ける方が無難かもしれません。
なお、この場合に提出する退職届(退職願)は以下のようなもので差し支えありません。
【退職届(退職願)の記載例】
株式会社○○
代表取締役○○ ○○ 殿
退職届
私は、一身上の都合により、△年△月△日をもって退職いたします。
以上
〇年〇月〇日
東京都〇区○○一丁目〇番〇号
○○ ○○ ㊞
(2)労働基準監督署に対して労働基準法違反の申告を行う
先ほども説明したように、たとえ就業規則に「退職する際は会社所定の様式で作成した退職届(退職願)を提出しなければならない」などと規定されていたとしても、法律で労働者に「退職の自由(民法627条,同628条,労働基準法137条)」が認められており、「強制労働の禁止(労働基準法5条)」や「奴隷的拘束の禁止(憲法18条)」も保障されていますので、適宜の様式で作成した退職届(退職願)を提出するなどして退職の意思表示を行えば問題なく退職することは可能です。
そのため、それでもなお「会社所定の様式」にこだわって退職を認めず労働者の退職を妨害するような会社があれば、その会社は労働者に対して法律上(または契約上)の根拠なく労働を強制しているということも言えますので、その会社は強制労働の禁止を規定した労働基準法第5条に違反することになることから、労働基準監督署に労働基準法違反の申告を行うことが可能になるものと考えられます(労働基準法第104条1項)。
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
労働基準監督署に労働基準法違反の申告を行い、監督署から勧告等が出されれば、会社の方でも法的根拠のない就業規則の規定に固執して「会社所定の様式」で作成した退職届(退職願)の提出を求める行為を止める可能性もありますので、適宜の様式で作成した退職届(退職願)を提出した後も会社側が退職を拒絶し就労を強要する場合には労働基準監督署への申告も考えた方がよいのではないかと思います。
なお、この場合に労働基準監督署に提出する労基法違反の申告書は、以下のような文面で差し支えないと思います。
【労働基準法104条1項に基づく労基法違反に関する申告書の記載例】
労働基準法違反に関する申告書
(労働基準法第104条1項に基づく)
○年〇月〇日
○○ 労働基準監督署長 殿
申告者
郵便〒:***-****
住 所:東京都〇〇区○○一丁目〇番〇号○○マンション〇号室
氏 名:申告 太郎
電 話:080-****-****
違反者
郵便〒:***-****
所在地:東京都〇区〇丁目〇番〇号
名 称:株式会社○○
代表者:代表取締役 ○○ ○○
申告者と違反者の関係
入社日:〇年〇月〇日
契 約:期間の定めのない雇用契約
役 職:特になし
職 種:製造
労働基準法第104条1項に基づく申告
申告者は、違反者における下記労働基準法等に違反する行為につき、適切な調査及び監督権限の行使を求めます。
記
関係する労働基準法等の条項等
労働基準法第5条
違反者が労働基準法等に違反する具体的な事実等
・申告者は〇年〇月〇日に上司である◆◆に2週間後の◇月◇日をもって退職する旨記載した退職届を提出したが、違反者は「就業規則の○条では会社所定の様式で作成した退職届を提出することが義務付けられてるんだから会社所定の様式で作成した退職届を提出しないと退職は認めない」と主張し、申告者の退職届の受け取りを拒否した。
・申告者は当該上司に対し「会社所定の様式」のひな型を提示するよう求めたが「今は忙しいから…」と言うのみでその後2週間が経過しても「会社所定の様式」を教えない。
・そのため申告者は再度適宜の様式で作成した退職届を作成し、当該上司に提出したが再度受け取りを拒否されたため〇年〇月〇日付けで作成した退職届を特定記録郵便で違反者に送付し、当該退職届は同年〇月〇日に違反者に配達された。しかしながら違反者は申告者の自宅に押し掛けるなどしていまだに復職を迫っている。
添付書類等
1.〇年〇月〇日に上司の◆◆に提出した退職届の写し 1通
2.〇年〇月〇日付けで特定記録郵便で送付した退職届の写し 1通
備考
特になし。
以上
(3)その他の対処法
以上の方法でも解決しない場合には、労働局に紛争解決援助の申し立てを行ったり、自治体や労働委員会の「あっせん」を利用したり、弁護士会と司法書士会が主催するADRを利用することも検討する必要があります。
また、案件によっては弁護士や司法書士に個別に依頼して裁判手続きで解決を図る必要がありますので、自力での解決が困難であることがわかった時点で早めに弁護士や司法書士に相談するよう心掛けてください。
なお、これらの対処法を取る場合の具体的な相談場所等についてはこちらのページでまとめていますので参考にしてください。