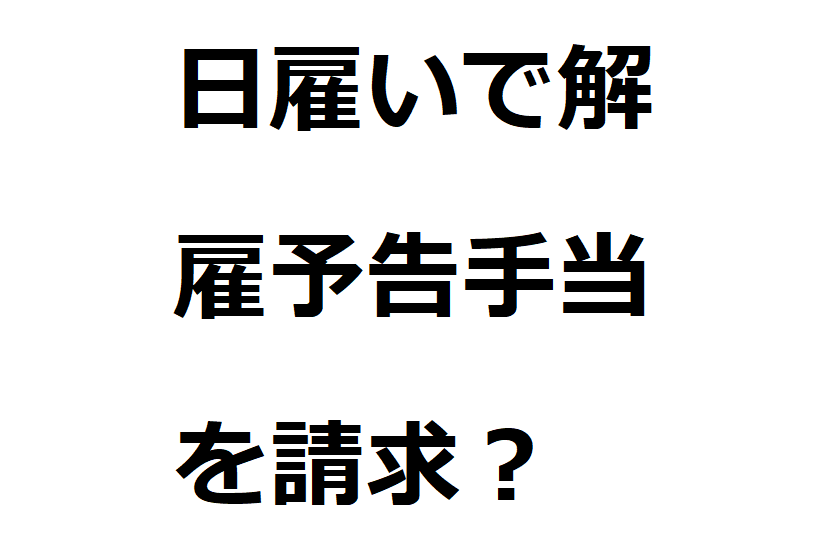雇い主から、その日その日で雇われてその日一日働き、その日の給料をその日払い(または数日後のまとめ払い)で受け取るような雇用形態を、一般に「日雇い」といい、そのような雇用形態で働く労働者を「日雇い労働者」と言います。
たとえば、早朝の駅前などに集合しておいて、工事関係者のトラックが到着するごとに「お前とお前乗れ」と体力のありそうな人から順に乗せられ、その日ごとに適宜の現場で働いて、夕方にその日の日給を受け取る(または働いた日数分の給料を後日まとめて受け取る)などの雇用形態がそれです。
このような日雇いの契約では、その日その日で雇用契約が成立し、その日その日で契約と退職(1日の契約期間満了)を繰り返しますから、仮に雇い主がその労働者を解雇しようと思った場合(例えば工事現場に連れて来たはいいもののいざ作業に就かせようと指示すると酩酊状態で指示に従えない場合など)であっても、その契約した当日に解雇することになりますので、解雇の事前に「解雇予告」を行うことは常識的に考えて困難です。
ですから、仮に日雇い労働者が雇い主から解雇される場合であっても、事前の解雇予告や解雇予告手当の支払いはなされないのが通常になっているわけですが、それが必ずしも許されるというわけではありません。
一定の場合には、日雇い労働者であっても雇い主に対して解雇予告手当の支払いを求めることができる場合があります。
日雇い労働者の場合は解雇予告手当の支払いを求めることができないのが原則
使用者が労働者を解雇する場合、解雇の効力が生じる30日前までに解雇予告を行うか、その解雇予告を省略する場合には30日に不足する日数分の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないことが労働基準法第20条で義務付けられています。
【労働基準法第20条】
第1項 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
第2項 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
第3項 前条第2項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
ですから、労働者が解雇された場合において、会社から30日前までに解雇の予告が行われていない場合には、その30日に不足する日数分の平均賃金(解雇予告手当)を支払うよう、会社に対して請求することができます。
しかし、前述したように、日雇い労働者の雇用契約は、「その日」に契約して「その日」に退職(1日の契約期間満了)し、それを日ごとに繰り返すものですから、そもそもその契約的に「解雇予告」は必要とされません。
そのため、法律では日雇い労働者の場合には、この労働基準法第20条第1項の解雇予告や解雇予告手当の支払いを除外しています。具体的には労働基準法の第21条です。
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
第1号 日日雇い入れられる者
第2号 2箇月以内の期間を定めて使用される者
第3号 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
第4号 試の使用期間中の者
ですから、日雇い労働者の場合には、たとえ即日解雇したとしても、会社に対して解雇予告手当の支払いを請求することはできないということになります。これが原則です。
なお、この点については『解雇予告・解雇予告手当の適用が除外される4つの雇用形態とは』のページでも詳しく解説しています。
日雇い労働者であっても「1か月以上継続勤務」している場合は解雇予告手当の支払いを求めることができる
前述したように、日雇い労働者の場合には労働基準法第21条で同法20条の解雇予告の規定の適用が排除されていますから、日雇い労働者が使用者から事前予告を受けずに即日解雇されたたとしても、使用者に解雇予告手当の支払いを請求することはできません。
しかし、これには例外があります。それはその日雇い労働者が「1か月を超えて引き続き使用されるに至った」ようなケースです。
労働基準法第21条は日雇い労働者について労働基準法第20条の適用を除外していますが、但し書きで「(日雇い契約の労働者)が1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合」にその適用除外を除外していますので、日雇い労働者が「1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合」には、原則に立ち戻って使用者に労働基準法第20条に基づいて解雇予告と解雇予告手当の支払いが義務付けられることになります。
つまり、日雇い契約で働く労働者であっても、1か月を超えて継続して同じ雇い主から雇用され続けている場合には、その後に日雇い先の会社から事前予告なく解雇された場合には、会社に対して「30日分の平均賃金(解雇予告手当)を支払え」と請求できることになるのです。
これは、「1か月を超えて引き続き使用されるに至った」ような場合には、日雇い契約であっても労働者は「次の1か月も契約が継続されるだろう」という期待が生じ、事前の予告なく解雇されれば不測の不利益を受けてしまうことになるので、労働者の保護のために、使用者に対して30日前の解雇予告とその予告をしない場合の解雇予告手当(30日に不足する日数分の平均賃金)の支払いを義務付けたものになります。
なお、この「1か月を超えて…」における「1か月」とは「休日を含む暦日の1か月」の意と解釈されていますので(※菅野和夫著「労働法(第8版)」弘文堂448頁)、30日連続で日雇い契約が結ばれている必要はありません。
ですからたとえば、日雇い労働者のAさんが、9月1日に会社Xとの間で日雇いの雇用契約を結び9月1日の勤務が終わった際に「明日も来れるなら来て」と言われて2日も勤務し、土日の休みをはさんで毎週5日間その日雇い契約が9月30日まで繰り返されたところで30日になって「明日から来なくていい」と言われて解雇された場合は「1か月を超えて引き続き使用されるに至った」ということにはなりませんから解雇予告手当の支払いを請求することはできませんが、この場合のAさんが10月1日に「明日から来なくていい」と言われて解雇された場合には、「1か月を超えて引き続き使用されるに至った」ということになりますので、30日の予告期間を置かずに即日解雇されたAさんは、会社Xに対して労基法第20条1項を根拠に「30日分の平均賃金(解雇予告手当)を支払え」と請求できることになります。
なお、平均賃金の計算方法やその他解雇予告手当の基本的な内容については『「解雇予告」また「解雇予告手当」とは何か(具体例と適用基準)』のページで詳しく解説しています。
日雇い労働者が解雇された場合に解雇予告手当の支払いを請求する方法
以上で説明したように、たとえ日雇い契約で働く労働者であっても「1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合」において30日の予告期間を置かずに解雇された場合には、解雇した会社に対して30日に不足する日数分の平均賃金(解雇予告手当)の支払いを請求することができます。
とは言っても、このようなケースで日雇い労働者が事前予告なく解雇され解雇予告手当も支払われない場合には、労働者の方で何らかの対処をしなければなりませんので、その場合の具体的な対処法が問題となります。