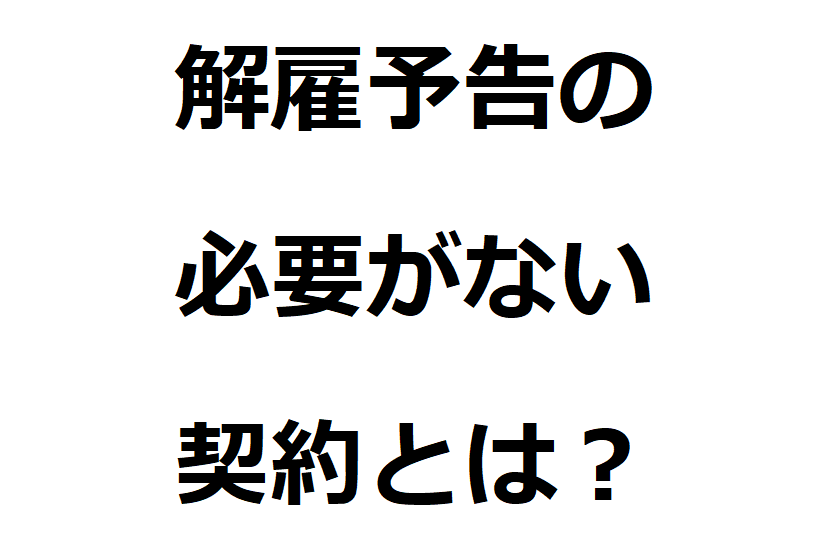労働者が使用者から解雇を言い渡される場合、解雇までの期間に応じて解雇予告がなされるか解雇予告が短縮された期間の平均賃金(いわゆる「解雇予告手当」詳細は→「解雇予告」また「解雇予告手当」とは何か(具体例と適用基準))の支払いが行われなければなりません(労働基準法第20条)。
【労働基準法第20条】
第1項 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
第2項 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
第3項 前条第2項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
この解雇予告と解雇予告手当を規定した労働基準法第20条は正社員だけでなくアルバイトやパート、契約社員や派遣社員等いわゆる非正規労働者の解雇にも適用されることは『「解雇予告」また「解雇予告手当」とは何か(具体例と適用基準)』のページでも詳しく解説しましたが、その契約形態によっては労働基準法第20条の適用が排除される場合も存在します。
そこでここでは、具体的にどのような雇用契約で労働基準法第20条の適用が排除され、使用者が解雇予告や解雇予告手当の支払いをしないことが認められるのか、という点について解説してみることにいたしましょう。
解雇予告・解雇予告手当の適用がない4つの雇用契約
解雇予告や解雇予告手当の支払い(※この点の詳細は→「解雇予告」また「解雇予告手当」とは何か(具体例と適用基準))は正社員の労働者だけでなく、アルバイトやパート、契約社員や派遣社員などにも適用されますので、使用者が労働者を解雇する場合には、基本的に解雇日の30日前までに解雇予告を行うか、30日の解雇予告期間を短縮する日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。
ただし、労働基準法第21条の規定から以下の5つの労働者に対しては解雇予告や解雇予告手当の支払いがなされなくても労働基準法第20条違反にならないことになっています。
- ① 日雇いで働く労働者(労基法21条1号)
- ② 契約期間が2か月以内の有期契約で働く労働者(労基法21条2号)
- ③ 季節的業務に4か月以内の有期契約で働く労働者(労基法21条3号)
- ④ 試用期間中の労働者(労基法21条4号)
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
第1号 日日雇い入れられる者
第2号 2箇月以内の期間を定めて使用される者
第3号 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
第4号 試の使用期間中の者
① 日雇いで働く労働者(労基法21条1号)
日雇いで働く労働者の労働契約は、その日その日で契約と解約を繰り返す労働契約となりますので30日前までに解雇予告をしなくても労働者の保護を損ないませんから、使用者は解雇予告や解雇予告手当の支払いをしなくても、労働者を解雇することが認められています(※ただし、その日の賃金は支払われなければならないでしょう)(労働基準法21条1号)。
ただし、日雇いで働く労働者であっても休日を含んで1か月以上継続して雇い入れられている事実がある場合には、たとえ日雇い労働者を解雇する場合であっても30日前までの解雇予告か短縮した日数分の解雇予告手当の支払いが義務付けられることになります(労働基準法第21条但し書き)。
これは、1か月以上継続して雇い入れられれば、たとえ日雇いであっても「来月も雇用されるだろう」という期待が生じ、解雇予告なしで解雇されれば不測の不利益を受けてしまうからです。
たとえば、9月1日から日雇いで働き始めた労働者が9月10日に雇い主から突然解雇されても解雇予告手当の支払いを請求することはできませんが、9月30日まで働いた時点で「今日で解雇するから明日から来なくていい」と言われた場合は、1か月以上継続して雇い入れられていることになりますので、雇い主に対して「30日分の平均賃金を支払え」と請求できることになります。
なお、この場合の具体的な請求方法については『日雇い労働者が解雇予告手当を貰えなかった場合の対処法』のページでさらに詳しく解説しています。
② 契約期間が2か月以内の有期契約で働く労働者(労基法21条2号)
2か月以内の有期契約で働く労働者を解雇する場合にも、使用者には解雇予告や解雇予告手当の支払いは義務付けられません(労働基準法21条2号)。
これは、有期労働契約(有期雇用契約)の契約期間が2か月以内と短い場合には、30日の予告期間を置かずに解雇したとしても労働者に与える影響は限定的で不測の不利益を与えることはないと考えられているからです。
たとえば、夏休み期間中の7月1日から8月末日までの期間限定で雇い入れられた労働者が7月31日にいきなり「明日から来なくていい」といきなり解雇されたとしても「30日分の平均賃金を解雇予告手当として支払え」とは請求できないことになります。
ただし、2か月以内の有期契約であってもその2か月の期間を満了して継続して雇い入れられているような場合には、解雇予告と解雇予告手当の支払いが適用されることになります(労働基準法第21条但し書き)。
2か月以内の有期契約であってもその契約が更新されれば「次の更新もあるだろう」という期待が生じるため解雇予告なしで解雇されれば不測の不利益を受けてしまう恐れがあるからです。
ですからたとえば、夏休み期間中の7月1日から8月末日までの期間限定で雇い入れられた労働者が夏休みが終わった後も引き続き契約を更新して9月以降も働いている状況で9月10日に「9月末で辞めてもらう」と雇い主から言われた場合は、30日の予告期間を置かずに解雇予告がなされたことになりますので、解雇予告に不足する10日分の平均賃金(解雇予告手当の支払い)を雇い主に求めることができます。
なお、この場合の具体的な請求方法については『バイト・パート・契約社員が解雇予告手当を貰えない場合の対処法』のページでさらに詳しく解説しています。
③ 季節的業務に4か月以内の有期契約で働く労働者(労基法21条3号)
季節的業務のために4か月以内の有期契約で雇い入れた労働者との有期契約についても、使用者には解雇予告や解雇予告手当の支払いが義務付けられていません(労基法21条3号)。
季節的業務で、かつ4か月以内と短期間なものであれば、たとえ30日の予告期間を置かずに解雇がなされたとしても、労働者が受ける不測の不利益は限定的と考えられるからです。
たとえば、5月から8月末までの収穫期だけ農場で雇い入れられた季節労働者などが、6月1日に雇い主から「今日で解雇する」と言われたとしても、解雇予告手当の支払いを求めることはできないということになります。
ただし、4か月以内の季節労働であっても、その4か月の期間を満了して継続して雇い入れられているような場合には、解雇予告と解雇予告手当の支払いが適用されることになります(労働基準法第21条但し書き)。
ですからたとえば、5月から8月末までの収穫期だけ農場で雇い入れられた季節労働者などが、夏場の収穫期が終わった後も引き続き契約を更新されて9月以降も働いている状況で9月10日に「9月末で辞めてもらう」と雇い主から言われた場合は、30日の予告期間を置かずに解雇予告がなされたことになりますので、解雇予告に不足する10日分の解雇予告手当の支払いを雇い主に請求することができることになります。
なお、この場合の具体的な請求方法についても『バイト・パート・契約社員が解雇予告手当を貰えない場合の対処法』のページでさらに詳しく解説しています。
④ 試用期間中の労働者(労基法21条4号)
試用期間中の労働者を解雇する場合も、使用者には解雇予告や解雇予告手当の支払いが義務付けられていません(労基法第21条4号)。
たとえば、「試用期間2週間」の契約で5月1日からアルバイトを始めた労働者が試用期間中の5月10日に雇い主から「明日から来なくていい」と言われたケースでは、試用期間を経過していないので雇い主に対して解雇予告手当の支払いを求めることはできないことになります。
ただし、試用期間中であっても、14日を超えた試用期間で実際に勤務している場合には、たとえ本採用を受けていない場合であっても解雇予告手当の支払いを求めることができます(労働基準法第21条但し書き)。
ですからたとえば、「試用期間1か月」の契約で5月1日からアルバイトを始めた労働者が試用期間中の5月15日に雇い主から「明日から来なくていい」と言われたケースでは、試用期間を満了して本採用には至っていない状態ですが、試用期間であっても14日を超えて勤務していますので、原則通り30日に満たない15日分の解雇予告手当の支払いを求めることができるということになります。
なお、この場合の具体的な請求方法については『試用期間中を理由に解雇予告手当が支払われない場合の対処法』のページでさらに詳しく解説しています。