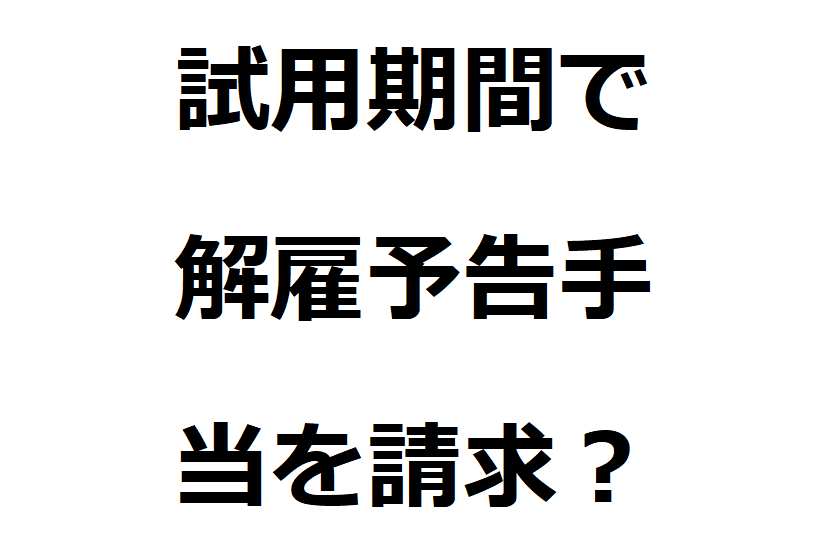使用者が労働者を解雇する場合、30日前までに解雇予告をするか、解雇予告期間を省略する日数分の平均賃金を支払わなければならないことが労働基準法第20条で義務付けられています(※詳細は→「解雇予告」また「解雇予告手当」とは何か(具体例と適用基準))。
【労働基準法第20条】
第1項 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
第2項 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
第3項 前条第2項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
しかし、使用者の中には解雇する労働者が「試用期間」にあることを理由にこの解雇予告手当をしないまま即日解雇する事例も見られます。
では、試用期間中の労働者が解雇された場合、解雇予告手当の支払いを受けることはできないのでしょうか。
試用期間の労働者は解雇予告手当の支払いを請求できないのが原則
前述したように、「試用期間」であることを理由に30日前の解雇予告をせず解雇予告手当の支払いもしないまま労働者を解雇する会社があるわけですが、基本的には「試用期間中」の労働者が解雇された場合、解雇予告手当の支払いはありません。
なぜなら、労働基準法第21条第4号が「試の使用期間中の者」について労働基準法第20条の適用を除外しているからです。
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
第1号 日日雇い入れられる者
第2号 2箇月以内の期間を定めて使用される者
第3号 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
第4号 試の使用期間中の者
これは「試用期間中」の労働者は試用期間満了時に本採用がなされない場合は退職しなければならないことをあらかじめ了承しているため、事前予告なしに解雇されたとしても不測の不利益を受ける恐れがないと考えられるからです。
ですから、使用者に採用されて働き始めたとしてもその「試用期間」が満了する「前」に解雇された場合には、使用者に対して「解雇予告手当を支払え」とは請求できないということになります。これが原則的な取り扱いとなります。
試用期間が14日を超える場合には、解雇予告手当の支払いを請求できる
このように、試用期間中にある労働者は労働基準法第20条の適用が排除されますので、事前予告なく突然解雇されたとしても、解雇予告手当を請求することはできません。
しかし、これには例外があります。その試用期間が「14日を超える場合」です。
労働基準法第21条但書は、「第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない」と規定していますので、試用期間が14日を超えている場合、また試用期間が14日を超えていなくても試用期間が延長されてその期間が14日を超えた場合には、労基法第21条の除外規定が除外されて、労働基準法第20条が適用されることになり、使用者に解雇予告や解雇予告手当の支払いが義務付けられることになります。
ですから、たとえば勤務先の会社から採用されて6月1日から「試用期間が1か月」の契約で働き始め、6月14日に会社から「明日から来なくていい」と言われて解雇された場合には14日を超えていないので解雇予告手当を請求することはできませんが、15日以降に解雇された場合には「14日を超えて引き続き使用されるに至った」ということになりますので、30日分の平均賃金(解雇予告手当)の支払いを求めることができるということになります。
また、たとえば勤務先の会社から採用されて6月1日から「試用期間2週間」の契約で働き始め、6月14日まで勤務したところで会社から試用期間を1週間延長させられて6月15日以降に解雇された場合には、「試用期間中の解雇」ではあっても「14日を超えて引き続き使用されるに至った」ということになりますので、その場合も会社に対して30日分の平均賃金の支払いを求めることができるということになります。
「14日間」とは休日も含めた総日数のこと
なお、この場合の「14日」というのは「休日も含めて14日」という意味になりますので(菅野和夫著「労働法(第8版)」弘文堂448頁)、実際に勤務した日数が14日に足らなくても、暦の上の日数が14日経過すれば、解雇予告手当の支払いを請求できるということになります。
「試用期間中」を理由に解雇予告手当を支払ってもらえない場合の対処法
以上で説明したように、試用期間中であっても「14日を超えて引き続き使用されるに至った」場合には、使用者に対して解雇予告手当の支払いを請求できます。
もっとも、実際に会社から解雇予告も解雇予告手当の支払いもないまま解雇されてしまった場合において会社が「試用期間中」を理由に解雇予告手当の支払いに応じない場合には、労働者の方で具体的な方法をとって対処しなければなりませんので、その場合の具体的な対処法が問題となります。
(1)「その解雇自体が有効か」という点を検討する
試用期間中の労働者が解雇予告も受けず解雇予告手当の支払いまま解雇された場合は、まず解雇予告手当の支払いを請求する前提として、「そもそもその解雇自体が有効なのか」という点を検討する必要があります。
なぜなら、そもそもその解雇が無効であるなら、その解雇の無効を主張して従業員としての地位を求めたり、解雇日以降に得られるはずであった賃金の支払いを求めることができるからです。
試用期間中の労働者が解雇された場合の解雇の効力等については、このサイトの「試用期間」のカテゴリーから適宜の記事を参照して確認してください。
なお、(2)以降で解説する対処法はあくまでも解雇が有効な場合、または解雇自体の効力を争わない場合にとりうる対処法です。そもそも解雇が無効であるにもかかわらず、(2)以降で説明する方法を用いて会社に対して解雇予告手当の支払いを請求してしまうと、「無効な解雇を追認した」と判断されて解雇自体の無効を主張することが困難になる場合がありますので注意が必要です。
(2)解雇予告手当の支払いを求める請求書を作成し会社に送付する
試用期間中の労働者が「14日を超えて引き続き使用されるに至った」状況にあるにもかかわらず、30日前までの解雇予告もなく解雇予告手当の支払いもないまま解雇された場合には、使用者に対して解雇予告手当の支払いを請求する通知書を作成して会社に送付するのも一つの対処法として有効です。
解雇予告手当の支払いに応じない会社に対して口頭で支払いを請求しても無視する会社がほとんどかもしれませんが、書面で正式に請求すれば、将来的な裁判や行政機関の介入を警戒して態度を改め支払いに応じるケースもあるからです。
なお、この場合に送付する通知書の文面は以下のようなもので差し支えないと思います。
(ア)試用期間が14日を超えている場合
甲 株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 殿
解雇予告手当の支払いを求める申入書
私は、〇年6月15日、貴社から事前の予告なく、同日付で解雇する旨の通知を受け、即日に解雇されましたが貴社からは、私が試用期間中にあったことを理由に解雇予告手当の支払いがなされておりません。
しかしながら、たしかに労働基準法第21条第4号は「試の使用期間中の者」について同法第20条の適用を除外していますが、同法第21条本文は「第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない」と規定していますので、試用期間中であってもその期間が14日を超えて勤務した場合には、同法第20条1項ないし2項に基づいて30日前の解雇予告を行うか、30日に不足する日数分の平均賃金を支払うことが使用者に義務付けられることになります。
この点、私と貴社の間で締結された労働契約における試用期間は6月1日から1か月間となっており、本件解雇を受けた当時すでに「14日間を超えて引き続き使用されるに至った」状態にありましたから、本件解雇には労働基準法第20条1項ないし2項が適用されることになり、貴社には30日前の解雇予告または30日分の平均賃金の支払いが義務付けられるものと考えられます。
したがって、30日前の解雇予告をせず、30日前の解雇予告手当の支払いもしないまま6月15日に即日解雇した貴社の行為は明らかに労働基準法第20条に違反していますから、直ちに平均賃金の30日分にあたる解雇予告手当の支払いを行うよう、申し入れいたします。
以上
〇年〇月〇日
〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号○○マンション〇号室
○○ ○○ ㊞
※送付した事実を証拠として残しておくため、コピーを取ったうえで、特定記録郵便など配達記録の残る郵送方法で郵送するようにしてください。