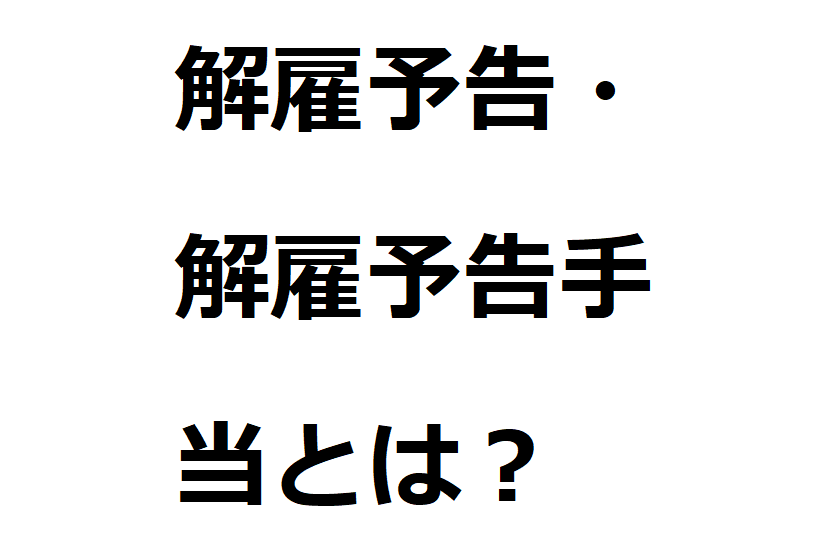労働基準法第20条では、労働者を解雇しようとする使用者に解雇の30日前までに「解雇予告」を行うこと、また30日前までの解雇予告をしない場合には短縮した日数分の「平均賃金(解雇予告手当)」を支払うことを義務付けています。
【労働基準法第20条】
第1項 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
第2項 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
第3項 前条第2項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
この解雇予告や解雇予告手当についてはメディアなどでも取り上げられることも多いため比較的多くの人がそれなりの知識を有していると思いますが、その詳細について若干勘違いして記憶している人も多いような印象があります。
そこでここでは、労働基準法第20条で規定された解雇予告と解雇予告手当の仕組みについて、改めて少し詳しく解説しておくことにいたしましょう。
解雇予告とは
解雇予告とは、使用者が雇い入れている労働者を解雇する場合に、その解雇日の30日前までに解雇の予告を行わなければならないと法律で義務付けられているその予告のことを言います。
これは、使用者に即日解雇を認めると労働者が生活の糧を失うことになり受ける不利益が甚大になるので、労働者の保護のために解雇するにしても少なくとも30日前までに予告することを使用者に対して義務付けたものです。
上に挙げたように、労働基準法第20条1項では解雇する場合に30日前までの解雇予告を行うことを義務付けていますので、使用者が労働者を解雇する場合には、その解雇日の30日前までに「〇月〇日で解雇しますよ」という解雇予告をしなければなりません。これが労働基準法第20条に言う「解雇予告」のことになります。
たとえば、会社Xが労働者Aを「6月30日付」で解雇しようとする場合には、会社Xは解雇日の30日前にあたる5月31日の午後12時12分59秒が経過するまでに、労働者Aに対して「6月30日をもって解雇します」と告知しなければならないわけです。これが「解雇予告」です。
解雇予告手当とは
解雇予告手当とは、解雇予告の期間を短縮する場合に使用者が労働者に支払うその短縮した日数分の平均賃金のことを言います。
これは、解雇の際に労働者の保護を図る必要から30日の予告期間が必要としても短縮した日数分の平均賃金を支払った場合にまで使用者側に労務の提供を義務付ける必要はないと考えられることから、解雇予告手当の支払いをした使用者に予告期間の短縮を認めるものです。
先ほど説明したように労働基準法第20条の規定から使用者が労働者を解雇する場合には30日前の解雇予告をすることが義務付けられますが、労働基準法第20条には「30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」とも規定されていますので、30日前の予告をしなくても短縮した日数分の「平均賃金」を支払えば、解雇予告の期間を短縮することができます。
そのため30日の予告期間を置かずに労働者を解雇したい会社では、解雇予告期間を短縮したい日数分の平均賃金を労働者に支払うことで解雇予告期間を短縮して労働者を解雇しようとします。その場合に労働者に支払われる平均賃金のことが「解雇予告手当」と呼ばれているのです。
たとえば先ほどの例で会社Xが労働者Aを6月30日に解雇しようとする場合には、その会社Xは30日前の5月31日までに解雇予告をしなければなりませんが、仮に会社Xが労働者Aに10日分の平均賃金を支払うのであれば、30日の解雇予告期間を10日短縮した6月10日までに解雇予告をすれば、会社Xは労働基準法第20条に違反することなく労働者Aを6月10日に解雇予告を通知することで6月30日に解雇することができることになります。
ですから、仮に会社Xが30日分の平均賃金を労働者Aに支払うのであれば、解雇予告は「0日」でも構わないことになりますので、たとえば会社Xが6月30日に30日分の平均賃金を支払うのであれば、解雇予告をすることなくその当日の6月30日にいきなり「今日で解雇します」と即日解雇しても、その解雇は労働基準法第20条違反にはならないということになります。
解雇予告手当の計算方法
会社から解雇予告手当が支払われる場合にその具体的な金額がいくらになるか、という点が問題になりますが、その金額は解雇予告期間の30日から短縮する日数分の「平均賃金」であって「賃金」ではありませんので注意が必要です。
平均賃金の計算方法は労働基準法の第12条に細かく規定されていますが、簡単に説明すると、その解雇予告の発生した直前の賃金締切日以前の3か月間における賃金の総額(ボーナスなどは除く)をその期間の総日数(出勤日数ではありません)で除して算出された金額が平均賃金となります。
ですから毎月の給料が一定の固定給の場合は平均賃金の計算は給料3か月分を直近3か月の総日数で割れば簡単に算出されますが、毎月の給料が変動するような賃金形態(たとえば日給月給制など)の場合は、直近3か月の勤務日数に応じて変動しますので計算方法に注意が必要です。
解雇予告手当は「解雇の効力発生日」に支払われなければならない
解雇予告手当は労働の対価として支払われるものではなく、解雇予告の期間を短縮させる際に支払いが法律によって義務付けられるものですので、その解雇予告手当の支払いは、解雇の効力が発生する日までに支払われる必要があります。
例えば前述の例で、6月30日に解雇する労働者に対して6月10日に解雇の予告をする場合の会社は10日分の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりませんが、その解雇予告手当は6月30日までに支払わなければならないことになります。
ですから、この場合に会社から「解雇予告手当は次の給料日に支払う」とか「解雇日の7日以内に支払う」などと言われて解雇日の6月30日までに解雇予告手当が支払われない場合には、その会社は労働基準法第20条に違反しているということになるでしょう。
なお、即日解雇(前の例で6月30日の当日に「今日で解雇する」と言われて解雇されるようなケース)の場合には、その解雇日当日(6月30日)に30日分の平均賃金が解雇予告手当として支払われないと、その会社は労働基準法第20条に違反しているということになります。
解雇予告・解雇予告手当の支払い義務は会社だけではなく個人事業主にも適用される
労働基準法は労働者を雇い入れた使用者に適用されますので、解雇予告や解雇予告手当の支払い義務についても会社(法人)だけでなく個人事業主にも適用されることになります。
ですから、たとえばフリーで活動しているイラストレーターが時給を払って手伝ってもらっている助手を解雇するような場合にも、解雇日の30日前までに解雇予告をしなければなりませんし、30日前までに解雇予告をしないのであればその30日に満たない日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払わならず、それをしない場合は労働基準法第20条違反として処罰の対象になります。
「日雇い」「2か月以内の短期契約」「季節的労働」「試用期間中」の場合は解雇予告と解雇予告手当は適用されない
解雇予告や解雇予告手当の支払いは正社員の労働者だけでなく、アルバイトやパート、契約社員や派遣社員などにも適用されますので、これらの非正規労働者が解雇される場合にも、解雇予告や解雇予告手当の支払いがなされなければなりません(※派遣の場合は派遣元の会社からの解雇予告または解雇予告手当の支払いがなされなければなりません)。
ただし、日雇いや契約期間が2か月以内の労働者、季節労働者、試用期間中の労働者については労働基準法第20条の適用が排除される場合がありますので注意が必要です(※詳細は→解雇予告・解雇予告手当の適用が除外される4つの雇用形態とは)。
使用者が解雇予告や解雇予告手当の支払いをしなくても良い場合
このように、使用者が労働者を解雇する場合には解雇の効力が生じる日の30日前までに解雇予告を行うか、解雇予告手当を支払うかしなければなりませんが、以下の2つの理由で解雇する場合には解雇予告や解雇予告手当の支払いをしなくても労働基準法第20条違反とならないケースがあります(労働基準法第20条第1項但し書き)。
イ)天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となって労働者を解雇する場合(労基法20条但書)
労働基準法第20条は但し書きで「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」には「この限りでない」と規定していますので、たとえば大地震や洪水被害などで会社の事業継続が不可能になって廃業するようなケースでは、労働者を即日解雇しても、解雇予告や解雇予告手当の支払いはしなくても良いということになります。
ただし、このように「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」に解雇予告をせずまたは解雇予告手当の支払いをすることなく解雇する場合には、使用者は労働基準監督署署長の認定を受けなければなりません(労働基準法第20条第3項、同法第19条第2項)。
ですから、仮に「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった」ことを理由に会社から解雇予告がなされず、また解雇予告手当の支払いもなされないまま解雇された場合において、会社がその解雇について労働基準監督署の署長からの認定を受けたことを証明できない場合には、その解雇された労働者は会社に対して解雇予告手当の支払いを請求できるということになります。
ロ)労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合(労基法20条但書)
また、「労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇」されるような場合にも、会社はその解雇する労働者に対して解雇予告や解雇予告手当の支払いをしなくてもよいことになっていますので(労働基準法第20条第1項但し書き)、たとえば労働者が懲戒解雇されるようなケースでは、解雇予告手当の支払いがなされないまま即日に解雇されるような場合もあると言えます。
ただし、使用者がこの「労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇」する場合にも、使用者は労働基準監督署署長の認定を受けることが義務付けられています(労働基準法第20条第3項、同法第19条第2項)。
ですから、仮に労働者が何らかの責められる行為をして懲戒解雇されるようなケースで、解雇予告や解雇予告手当の支払いがなされない場合であっても、その会社が「労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する」際に解雇予告や解雇予告手当の支払いをせずに即日解雇することについて労働基準監督署の署長の認定を受けていない場合には、その懲戒解雇される労働者は、会社に対して解雇予告手当の支払いを請求することができるということになります。
解雇予告手当が支払われても無効な解雇が有効になるわけではない
労働基準法第20条の解雇予告や解雇予告手当の支払い義務の規定は、無効な解雇を有効にする効力を生じさせるものではありませんので、そもそも無効な解雇である場合にはたとえ解雇日の30日前までに解雇予告がなされるか解雇予告期間を短縮した日数分の解雇予告手当が支払われていたとしても、その解雇自体が無効になりますので退職せずに引き続き勤務することは可能です。