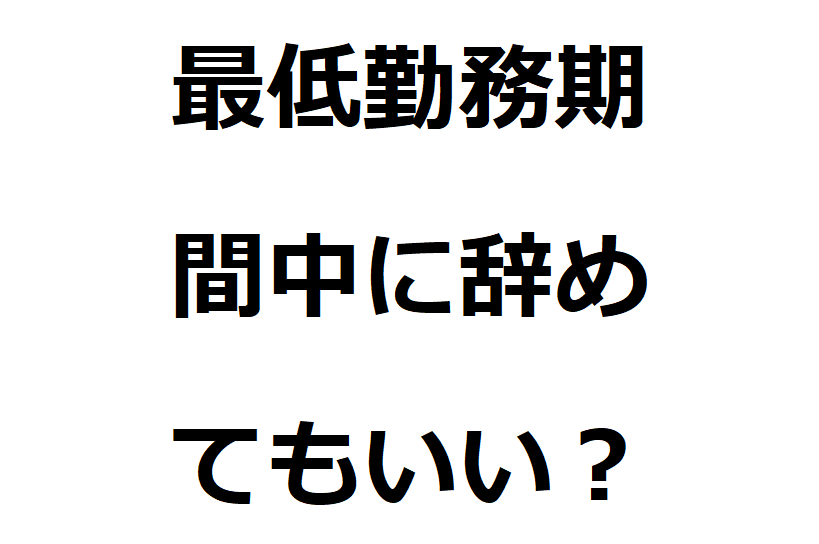アルバイトやパートなどいわゆる非正規雇用の求人の中には、ごく稀に「最低勤務期間」が設定されているものがあります。
たとえば、下のような有期雇用契約(有期労働契約)の労働者を募集する求人で、半年間は必ず勤務することを条件とする最低勤務期間を設けて採用を掛けるようなものが代表的な例としてあげられます。
【勤務時間】9:30~18:00(休憩時間1時間)※日曜定休です!【シフト】週3日、1日4h~OK、4時間未満は要相談【契約期間】2年間、希望により契約更新可【最低勤務期間】最低6か月
このような求人に応募して採用を受けた場合、労働者としては「最低でも6か月間はその会社で働かなければならない」ということを承諾したことになりますから、仮に6か月が経過する前に自己都合で退職してしまうとなると会社側から契約違反を理由に損害賠償請求を受けてしまう危険性があるとも思えます。
では、このような最低勤務期間が設定されている求人に応募して採用を受け実際に働き始めた場合、その最低勤務期間内に退職することはできないのでしょうか?
「最低勤務期間」の定めは「無効」と考えて差し支えないのが原則
結論から言うと、労働者と使用者(雇い主)との間で結ばれる「最低勤務期間」に関する合意は法律的に考えれば基本的に「無効」と考えられますので、仮に「最低勤務期間」に合意して雇用契約(労働契約)を結んだとしても、最低勤務期間の途中で退職することができなくなるわけではない、ということになります。
なぜかというと、法律上はたとえ働く期間が一定の期間に限定された期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)では、「やむを得ない事由」がある場合や「契約期間の初日から1年が経過した後」であれば、労働者の一存で自由に退職することが認められているからです。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
期間の定めのある労働契約(中略)を締結した労働者(中略)は、(中略)民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
先ほど挙げた求人例のように、働く期間が「〇年間(〇か月間)」とか「〇年〇月~〇年〇月まで」といったように一定の期間に限定されている雇用契約(労働契約)は「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」と呼ばれますが、この「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」として雇われる場合には、労働者はその契約期間中、使用者(雇い主)に対して労働力を提供しなければならないという雇用契約(労働契約)上の債務(義務)を負担していることになりますので、「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」で働き始めた場合には、その契約期間の途中で退職することはできません。
そのため、もし「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」で働く労働者が契約期間の途中で退職してしまった場合において会社に何らかの損害が発生した場合には、契約期間の途中で退職した労働者は雇用契約(労働契約)の債務不履行責任が発生し使用者(雇い主)に対してその損害を賠償しなければならないことになってしまうでしょう。
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
ですから、たとえば先ほどの求人例のような「契約期間が2年」として雇い入れられた場合に、2年が経過する前に退職してその退職したことによって会社に損害が発生した場合には、会社に対してその損害を弁償しなければならなくなってしまうのが原則的な取り扱いとなります。
しかし、このような適用をすべての場合に強制してしまうと、使用者は「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」で労働者を雇用しさえすれば労働者が損害賠償に応じる経済的な余裕がないことを利用して、容易にその意思に反して労働者を強制的に就労させることができることになってしまい、「強制労働の禁止」を規定した労働基準法5条や「奴隷的拘束の禁止」を保障した憲法18条に反する結果となり不都合が生じてしまいます。
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
そのため、法律では「やむを得ない事由がある場合」と「契約期間の初日から1年が経過した場合」に限って、契約期間が満了する前であっても労働者の方で自由に退職することができるようにしているわけです。
そして、この「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」における「やむを得ない事由」がある場合と「契約期間の初日から1年」が経過した場合における労働者の退職を認めた民法628条と労働基準法137条は、どちらも憲法18条の「奴隷的拘束の禁止」を具現化する法律として強行法規と一般に解釈されていますから、これに反する当事者間の合意は全て「無効」と判断されるのが通常です。
そうすると、「最低勤務期間」の約定は「労働者が最低勤務期間は退職できない」ことを使用者(雇い主)と労働者の間で合意する契約となりますから、その「最低勤務期間」の合意は自体が「やむを得ない事由」がある場合に退職することを認めた民法628条に、また「契約期間の初日から1年」が経過した後の退職を認めた労働基準法137条に反することになります。
したがって、「最低勤務期間」の合意自体が「無効」と判断されますから、仮に「最低勤務期間」が定められている求人や雇用契約に合意して働き始めた場合であっても、その「最低勤務期間」の途中で退職して何ら問題ない(最低勤務期間が経過する前に退職し会社に損害が発生してもその損害を賠償しなければならない責任は発生しない)ということになるのです。
「最低勤務期間」の合意が有効と判断されるケース
以上で説明したように「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」では「やむを得ない事由がある場合」と「契約期間の初日から1年が経過した後」については労働者の方で自由に退職することが法律で認められていますから、「最低勤務期間」の合意は「無効」と判断して差し支えないといえますが、一定のケースでは「最低勤務期間」の合意が「有効」と判断される可能性もあるので注意が必要です。
たとえば、働き始める際に契約期間が具体的に「〇年〇月~〇年〇月まで」というように定められていない雇用契約で「最低勤務期間」が設定されているようなケースです。
契約期間が「〇年間(〇か月間)」とか「〇年〇月~〇年〇月まで」というように一定の期間に定められていない場合、その雇用契約は「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」と解釈されますが、その退職については民法627条が適用となり、労働者はいつでも自由に退職することができるのが原則です。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
しかし、この「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」として雇い入れられたうえで「最低勤務期間」が定められた場合には、雇用契約の内容としては「最低勤務期間という有期雇用契約」がいったん結ばれ、そのうえで「無期労働契約」が結ばれたという解釈も場合によっては成り立つ可能性が生じてしまうでしょう。
たとえば、アルバイトで雇われた際に契約期間が定められなかった場合、使用者(雇い主)と労働者の間で「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」が結ばれたものと解釈されますが、仮にその場合に「6か月間」の「最低勤務期間」が設定されていたとすると、「最低でも6か月間は退職しない」ということを誓約したうえで働き始めることになりますから、「6か月間」の「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」が結ばれたうえで6か月経過後に「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」に自動的に移行する、という2つの雇用契約が結ばれたという解釈も成り立つことになってしまいます。
そうすると「最低勤務期間6か月」という合意も「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」として「有効」と判断されることになりますので、その「最低勤務期間」の6か月間は退職が制限されるというケースもありえるかもしれません。
もちろん、このようなケースで全ての場合に「最低勤務期間」の合意それ自体が「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」として有効と判断されるわけではありません。
しかし、ケースによっては「最低勤務期間」の合意自体が独立した「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」と認定され「有効」と判断される可能性もありますので、その点は注意が必要といえます。
「最低勤務期間」があることを理由に退職を拒否された場合の対処法
以上で説明したように、「最低勤務期間」の合意は例外的なケースで独立した「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」と解釈されて有効と判断される可能性はありますが、ほとんどの場合は「無効」と判断されるものと考えられますので、「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」において「最低勤務期間」について合意して働き始めた場合には「最低勤務期間」が満了する前であっても「やむを得ない事由」があるか「契約期間の初日から1年」が経過した後であれば会社側の承諾なく自由に退職することができる、と考えて基本的には差し支えないということになります。
もっとも、このような法律上の解釈があるとしても、全ての会社の経営者や役職者がその法律を理解しているわけではありませんので、「最低勤務期間」の合意があることを根拠に最低勤務期間が経過する前の退職を拒否し就労を強制する会社も存在しているのが実情です。
そのため最低勤務期間が設定された雇用契約で最低勤務期間が経過する前の退職が姜妃された場合に具体的にどのように対処すればよいか、という点が問題となります。
(1)郵送で退職届(退職願)を送り付ける
使用者(雇い主)側が「最低勤務期間」の合意があることを理由に退職を拒否している場合には、退職届(退職願)を郵送で会社に送り付け、それ以降は出社しないようにするのも一つの対処法として有効です。
先ほども説明したように、仮に「最低勤務期間」の合意があったとしても、その合意は「無効」と考えて差し支えないと考えられますから、「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」で雇用されている場合には、「最低勤務期間」の途中であっても「やむを得ない事由」があるか「契約期間の初日から1年」が経過した後であればいつでも自由に退職の意思表示を行って退職することができるということになります。
この点「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」の退職の場合には退職の意思表示に2週間の予告期間を設けることが法律で定められていますが(民法627条)、「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」における「やむを得ない事由」がある場合または「契約期間の初日から1年」が経過後の退職については法律ではそのような予告期間は要求されていませんので(民法628条、労働基準法137条参照)、「いつでも自由に」退職の意思表示を行って退職することが可能です。
ですから、「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」で働く労働者が「最低勤務期間」の合意を無視して退職の意思表示を行う場合にも、退職届(退職願)を提出した時点ですぐに退職の効果が生じることになりますから、退職届(退職願)を提出した日の翌日からは一切出社しなくても特に問題は生じないでしょう。
ただし、後に裁判になった場合に会社側が「退職届(退職願)は受け取っていない」などと反論してきた場合は労働者側で「退職届(退職願)を提出した」ということを立証しなければなりませんので、会社側が退職届(退職願)の受け取りを拒否しているようなケースでは「退職届(退職願)を提出した」という事実の証拠を残しておくためにも、「手渡し」ではなく客観的な証拠の残る「郵送」で送付しておく方が無難です。
できれば、客観的な証拠が残るよう、提出する退職届(退職願)のコピーを取ったうえで特定記録郵便など「配達された」という記録が残される郵送方法で送付するこようにし、将来的に裁判に発展することが確実な事情がある場合には内容証明郵便で退職届(退職願)を送り付けることも考えたほうがよいかもしれません。
なお、実際に使用者(雇い主)に提出する退職届(退職願)は以下のようなもので差し支えありません。
【退職届(退職願)の記載例】
株式会社○○
代表取締役○○ ○○ 殿
退職届
私は、一身上の都合により、△年△月△日をもって退職いたします。
以上
〇年〇月〇日
東京都〇区○○一丁目〇番〇号
○○ ○○ ㊞
(2)労働基準監督署に対して労働基準法違反の申告を行う
先ほども説明したように、「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」であっても「やむを得ない事由」や「契約期間の初日から1年」が経過した後は労働者の一方的な意思表示でいつでも自由に退職することが法律で認められていますから(民法628条、労働基準法137条)、これに反する当事者間の合意と解釈される「最低勤務期間」の合意は、「強制労働の禁止」を規定した労働基準法5条に違反するものと判断することが可能です。
この点、使用者(雇い主)が労働基準法に違反する場合には、労働基準法104条1項の規定に基づいて、労働基準監督署に労働基準法違反の申告を行うことが可能になるものと考えられますから(労働基準法第104条1項)、その「最低勤務期間」の合意があることを理由に使用者(雇い主)が退職を拒否するような場合には、労働基準監督署に対して労働基準法違反の申告を行うことができるということになるでしょう。
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
労働基準監督署に労働基準法違反の申告を行い、監督署から勧告等が出されれば、会社の方でも「最低勤務期間」の合意があることを理由にした退職妨害を止める可能性もありますから、退職届(退職願)を提出した後も会社側が退職を拒絶し就労を強要する場合には労働基準監督署への申告も考えた方がよいのではないかと思います。
なお、この場合に労働基準監督署に提出する労基法違反の申告書は、以下のような文面で差し支えないと思います。
【労働基準法104条1項に基づく労基法違反に関する申告書の記載例】
労働基準法違反に関する申告書
(労働基準法第104条1項に基づく)
○年〇月〇日
○○ 労働基準監督署長 殿
申告者
郵便〒:***-****
住 所:東京都〇〇区○○一丁目〇番〇号○○マンション〇号室
氏 名:申告 太郎
電 話:080-****-****
違反者
郵便〒:***-****
所在地:東京都〇区〇丁目〇番〇号
名 称:株式会社○○
代表者:代表取締役 ○○ ○○
申告者と違反者の関係
入社日:〇年〇月〇日
契 約:期間の定めのある雇用契約(契約期間2年)
役 職:特になし
職 種:製造
労働基準法第104条1項に基づく申告
申告者は、違反者における下記労働基準法等に違反する行為につき、適切な調査及び監督権限の行使を求めます。
記
関係する労働基準法等の条項等
労働基準法第5条
違反者が労働基準法等に違反する具体的な事実等
・申告者は○年〇月から契約期間2年間の約定で違反者に雇用されていたが、入社して3か月が経過した〇年〇月に同居する母親の介護が必要となったため、同年〇月〇日付けで退職する旨記載した退職届を作成し、〇年〇月〇日に上司である◆◆に提出した。
・これに対して違反者は、申告者が入社する際に「最低勤務期間を6か月間」とする誓約書に署名押印していることを理由として、「最低勤務期間が経過するまでは退職は認められない」と主張し、退職届の受け取りを拒否した。
・そのため申告者は〇年〇月〇日付けで作成した退職届を特定記録郵便で違反者に送付し(当該退職届は同年〇月〇日に違反者に配達されている)退職希望日の◇月◇日以降、出社しないようにしたが、違反者は申告者の自宅に押し掛けるなどしていまだに復職を迫っている。
添付書類等
1.〇年〇月〇日に上司の◆◆に提出した退職届の写し 1通
2.〇年〇月〇日付けで特定記録郵便で送付した退職届の写し 1通
備考
特になし。
以上
(3)その他の対処法
以上の方法でも解決しない場合には、労働局に紛争解決援助の申し立てを行ったり、自治体や労働委員会の「あっせん」を利用したり、弁護士会と司法書士会が主催するADRを利用することも検討する必要があります。
また、案件によっては弁護士や司法書士に個別に依頼して裁判手続きで解決を図る必要がありますので、自力での解決が困難であることがわかった時点で早めに弁護士や司法書士に相談するよう心掛けてください。
なお、これらの対処法を取る場合の具体的な相談場所等についてはこちらのページでまとめていますので参考にしてください。