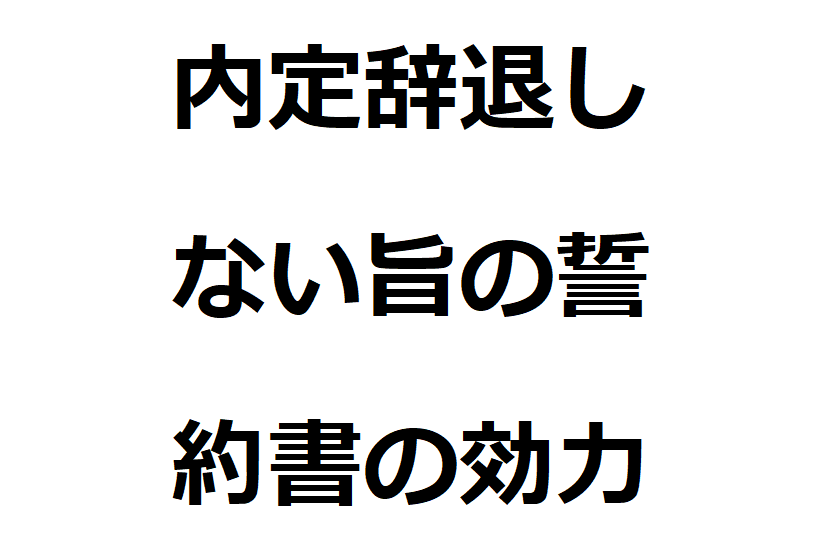就職を希望する企業から採用内定を受ける際に「内定を辞退いたしません」とか「入社予定日に必ず入社することを制約します」などと記載された誓約書に署名押印を求められるケースがあります。
内定を出す企業としては、内定者に内定を辞退されてしまうと採用活動に費やした時間と経費が無駄になってしまいますので、内定を出した内定者についてはすべて入社予定日から就労を開始してもらいたいと思うのは当然です。
そのため、内定を出す一部の企業で、内定者が入社予定日が到来するまでの間に内定を辞退しないよう「内定を辞退しないこと」を誓約させるケースがあるのです。
しかし、このような誓約は内定者にとっては大きな負担となります。
なぜなら、内定者の多くは複数の企業の面接を受けたうえでそのうち最も条件や魅力のある企業に就職したいと考えるのが通常であり、特定の内定先企業から「内定を辞退しない」ことを誓約させられてしまうと、他の企業から内定を受けた場合に希望する会社に入社することができなくなってしまうからです。
では、このように内定先企業から「内定を辞退しません」というような誓約書にサインを求められそれに応じてしまった場合、具体的にどのように対処すれば内定を辞退することができるのでしょうか?
「内定を辞退しない」旨の誓約は無効
このように、内定先の企業によっては内定者に対して「内定を辞退しません」などといった誓約書にサインさせ内定を辞退することを制限するケースがありますが、結論から言うと、そのような誓約は無効と判断されますので、仮にそのような誓約に合意して内定を受けた場合であっても、内定者が一方的な意思表示によって内定を辞退することができるということになります。
なぜそのような結論に至るかというと、企業から採用内定を受けた時点で内定者と内定先異業との間に有効に労働契約(雇用契約)が生じることになるからです。
「採用内定」によって企業との間に有効に労働契約(雇用契約)が生じるとすれば、入社予定日が到来する前に「内定を辞退」する行為は企業との間で生じた労働契約(雇用契約)を解約する「退職」と同じです。
この点、法律では労働者の「退職の自由」が明確に保障されており「内定辞退の自由」も当然に保障されることになりますから、それに反する「内定の辞退はしない」旨の誓約書は無効と判断して自由に内定を辞退することができるということになるのです。
(1)採用内定を受けた時点で企業との間に労働契約が有効に成立する
「採用内定」の法的性質には若干の争いがありますが、過去の最高裁の判例では「採用内定」を「入社予定日を就労開始日とする始期付きの解約権留保付き労働契約」に当たるとする解釈が採用されています。
企業から「採用内定」が出された場合、内定者に特段の問題がなければ内定先企業は内定者を入社予定日から入社させなければなりませんので、「入社予定日」は単に「就労を開始する日」にすぎず採用内定が出された時点で有効に労働契約(雇用契約)が結ばれていることになると考えることができますが、内定者に経歴詐称や不良行為(※入社予定日までの間に逮捕されるなど)があれば内定先企業の一方的な判断によって内定を取り消すことができる点を考えるとその「採用内定」によって結ばれる労働契約(雇用契約)は企業の側に「解約権」が「留保」されているということになります。
そのため、「採用内定」は「入社予定日を就労開始日とする始期付きの解約権留保付き労働契約」であると解釈されるわけです。
(2)内定の辞退は「退職」と同じ
「採用内定」が「入社予定日を就労開始日とする始期付きの解約権留保付き労働契約」であるとすれば、入社予定日は単に「就労を開始する日」にすぎないことになり、企業から「採用内定」が出された時点で内定者との間に有効に労働契約(雇用契約)が成立することになりますから、「採用内定」を受けた後に「内定を辞退」する行為は「退職」と同じ扱いを受けることになります。
なぜなら、「内定の辞退」は「採用内定」によって生じる「労働契約(雇用契約)」を内定者の一方的意思表示によって「解約」しその契約関係から離脱することを目的としたものになりますので、「採用内定」によって有効に労働契約(雇用契約)が発生している以上、その効果は労働契約(雇用契約)関係にある労働者が会社を辞める行為となる「退職」と同じ行為と言えるからです。
(3)退職の自由が認められる以上、内定辞退の自由も保障される
この点、退職については民法627条に規定があり、労働者はいつでも自由に退職の意思表示を行うことができ、その退職の意思表示を行って2週間が経過した時点で無条件に「退職」の効果が生じ使用者(雇い主)との労働契約(雇用契約)関係から離脱することが認められています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
そうであれば、「内定の辞退」も「退職」と同じ効果を生む以上、内定者が「内定を辞退」する場合もこの民法627条の規定に従って「いつでも」「自由に」、「内定を辞退」することができるのは当然といえます。
もっとも、627条1項に規定される「2週間」の猶予期間については、労働者から退職を申し入れられた使用者において代わりの労働者を確保する時間を確保するためのものであり、「採用の辞退」の場面のように入社予定日が到来する前で未だ就労を開始していないケースでは猶予期間を設ける必要は生じません。
ですから、「内定の辞退」をする場合は、2週間の猶予期間を置かずとも、「内定辞退」の申入れをした時点で内定先企業との「採用内定」によって生じた労働契約(雇用契約)を一方的に即日に解約することができるということになるでしょう。
いずれにせよ、「内定の辞退」が民法627条1項で保障されており、内定者は入社予定日が到来するまでの期間は「いつでも」「自由に」一方的意思表示によって内定を辞退することができるということになります。
(※なお、入社予定日が到来した後は、民法627条1項にあるように2週間の猶予期間さえ置いておけばいつでも自由に「退職」することができるということになります)
(4)退職の自由を保障した民法627条1項に反する当事者間の合意は無効
以上のように、「採用内定」が「退職」と同列に扱われる以上「内定の辞退」は民法627条1項により保障されているといえますので、内定者は会社側の承諾なしにいつでも自由に内定の辞退ができるということになります。
この点、このページの冒頭に述べたように「内定を辞退しません」といった誓約書に署名している場合にも内定の辞退が認められるかという点が問題となりますが、そのような誓約に合意している場合であっても内定を辞退することは可能です。
なぜなら、退職の自由を規定した民法627条1項は強行法規と考えられており、これに反する当事者間の合意はすべて無効と判断されるからです。
民法627条1項で労働者に「いつでも自由に」退職することを認めた趣旨は、「奴隷的拘束の禁止」を保障した憲法18条を具現化するところにありますが、仮にこれに反する当事者間の合意を有効としてしまうと、使用者(雇い主)が圧倒的に強い立場にある労働契約(雇用契約)の性質上、そのような誓約書にサインを求めることによって容易に労働者を「奴隷的に拘束」することができることになり不都合な結果が生じてしまいます。
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
そのため、民法627条1項に反する当事者間の合意は全て無効と判断されることになりますから、仮に内定者が「内定を辞退しません」という誓約の意味を十分に理解し本心から望んでその誓約に合意しサインしたとしても、その誓約自体が無効となり、内定者はいつでも自由に内定を辞退することができるということになるのです。
「内定を辞退しない」旨の誓約書にサインした後に内定辞退する場合
以上で説明したように、「採用内定」によって内定先企業との間に労働契約(雇用契約)が発生し、「内定の辞退」が「退職」と同じ効果を生じさせる以上、内定者が内定を辞退することは民法627条1項で保障されますので、仮に「内定を辞退しません」というような誓約書に署名捺印していたとしても、そのような誓約は無効なものとして、いつでも自由に「内定を辞退」することができるということになります。
この点、「内定を辞退しません」という誓約書にサインした後に、具体的にどのような方法で内定を辞退すればよいかという点が問題となりますが、これはそのような誓約書にサインしたという事実に関係なく、単に「内定を辞退する」旨を記載した通知書を送付すれば足ります。
もちろん、口頭で「内定を辞退します」というだけでも(例えば電話などで)意思表示としては有効ですが、「内定を辞退しません」というような誓約書にサインさせるような会社はブラック体質を持っている蓋然性が高いといえますので、後日の紛争を防ぐ意味でも確実に会社側に「内定の辞退に関する意思表示を行った」という客観的な証拠が残される「書面」の形で行っておく方がよいと思います。
なお、この場合に内定先企業に送付する「内定辞退の申入書」の記載例は以下のような文面で差し支えないでしょう。
○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 殿
内定辞退申入書
私は、〇年〇月〇日、同年△月△日付け採用内定通知書の送付を受ける方法によって貴社から採用内定の通知を受けましたが、都合により当該採用内定を辞退いたします。
以上
◇年◇月◇日
〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号○○マンション〇号室
○○ ○○ ㊞
「内定を辞退しない」旨の誓約書にサインしていることを理由に内定の辞退を拒否された場合の対処法
内定辞退申入書等を郵送しても内定先企業が「内定を辞退しない」旨の誓約書にサインしていることを根拠に内定の辞退を認めず入社予定日からの終了を強要するような場合には、労働基準監督署に労働基準法違反の申告を行うというのも一つの方法として有効です。
先ほども説明したように、「内定の辞退」は民法627条1項で保障されていますので、仮に「内定を辞退しない」旨の誓約書にサインしていたとしても、そのような誓約書に効力はなく無効と言えます。
そうすると、仮にそのような誓約書にサインしていたとしても、そのような誓約は無視して内定者の一存によって内定の辞退を申し入れることができ、その内定辞退の申し入れが内定先企業に到達した時点で内定先企業との間に成立していた労働契約(雇用契約)は有効に解約されることになります。
それにもかかわらず、内定先企業がそのような法律上の解釈を無視して内定者に対して入社予定日からの就労を強要しているとすれば、それは内定先企業が法律上および契約上の根拠なくして内定を辞退した人物に対して就労を強制していることになりますから、それはすなわち「強制労働の禁止」を規定した労働基準法第5条に違反して、内定を辞退した内定者に対して「強制労働を強いている」ということになるでしょう。
この点、労働基準法に違反する事業主に対しては、労働基準法の104条の規定に基づいて、労働基準監督署に対して労働基準法違反の申告を行うことができることになっていますので、「内定を辞退しない」旨の誓約書にサインしていることを理由として内定を辞退した内定者が就労を強制されている場合には、その内定先企業が労働基準法5条に違反していることを理由に労働基準監督署に対して違法行為の是正申告を行うことができるということになります。
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
労働基準監督署に労働基準法違反の申告を行い、監督署から勧告等が出されれば、内定先企業の方でも執拗な入社の強要を止める可能性もありますので、内定先企業からの入社の強要が止まない場合には、監督署への申告も考えた方がよいのではないかと思います。
なお、この場合に労働基準監督署に提出する労基法違反の申告書は、以下のような文面で差し支えないと思います。
【労働基準法104条1項に基づく労基法違反に関する申告書の記載例】
労働基準法違反に関する申告書
(労働基準法第104条1項に基づく)
○年〇月〇日
○○ 労働基準監督署長 殿
申告者
郵便〒:***-****
住 所:東京都〇〇区○○一丁目〇番〇号○○マンション〇号室
氏 名:申告 太郎
電 話:080-****-****
違反者
郵便〒:***-****
所在地:東京都〇区〇丁目〇番〇号
名 称:株式会社○○
代表者:○○ ○○
申告者と違反者の関係
入社日:(※内定日:〇年〇月〇日)
契 約:期間の定めのない雇用契約
役 職:特になし
職 種:営業
労働基準法第104条1項に基づく申告
申告者は、違反者における下記労働基準法等に違反する行為につき、適切な調査及び監督権限の行使を求めます。
記
関係する労働基準法等の条項等
労働基準法第5条
違反者が労働基準法等に違反する具体的な事実等
・申告者は〇年〇月〇日、自宅あてに送付された違反者からの内定通知書によって採用内定の通知を受けたが、同年〇月〇日、内定辞退通知書を違反者に送付する方法をもって当該採用内定を辞退する旨の意思表示を行った。
・これに対して違反者は、申告者が違反者からの採用内定を受けた際に「自己の都合で採用内定を辞退することなく入社予定日から就労することを誓約いたします」旨記載された誓約書に署名捺印していることを理由に内定の辞退を受け入れず、採用担当者が頻繁に申告者の携帯電話に電話を掛け、また申告者の自宅に押し掛けるなどして入社予定日にあたる〇年〇月〇日からの就労を強要している。
しかしながら、かかる誓約は民法627条1項に違反し無効と言えるから、違反者の行為は強制労働の禁止を規定した労働基準法5条に違反する。
添付書類等
1.〇年〇月〇日に違反者から通知を受けた採用内定通知書の写し 1通
2.〇月〇日付けで違反者に通知した内定辞退申入書の写し 1通
備考
特になし。
以上
(3)その他の対処法
上記のような方法で対処しても会社側が内定の辞退を認めなかったり入社予定日から就労を強制するような場合は、会社側が自社の解釈によほど自信があり労働基準法5条に違反しないという確固たる確信があるか、ただ単にブラック体質を有した法律に疎い会社かのどちらかである可能性が高いと思いますので、なるべく早めに法的な手段を取って対処する方がよいでしょう。
具体的には、労働局に紛争解決援助の申し立てを行ったり、自治体や労働委員会の”あっせん”の手続きを利用したり、弁護士会や司法書士会が主催するADRを利用したり、弁護士や司法書士に依頼して裁判を行うなどする必要があると思いますが、その場合の具体的な相談先はこちらのページでまとめていますので参考にしてください。