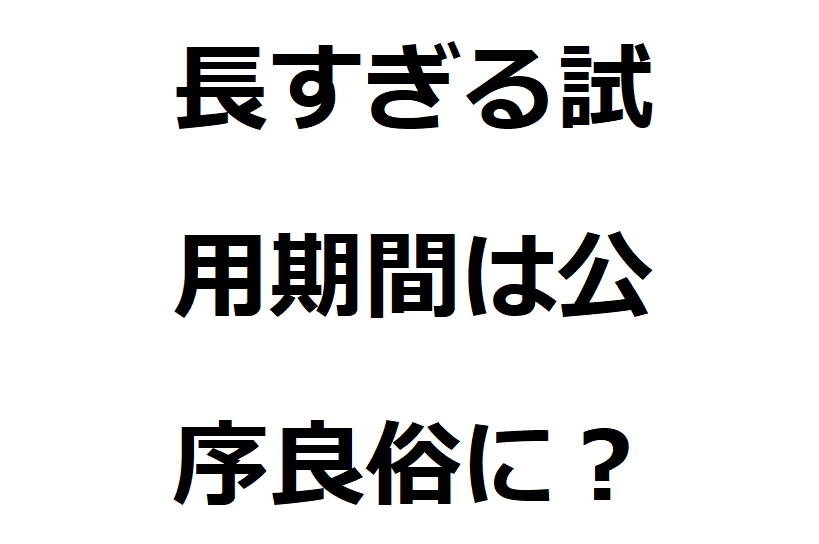労働者を採用した企業では、採用した労働者に「試用期間」を設けることがあります。
たとえば、労働者Aを採用した企業Xが、3か月間の試用期間を設定してその3か月の間にAさんを評価し、3か月の試用期間経過後に評価した結果本採用すると判断した場合は労働者として正式に雇い入れ、本採用しないと判断した場合には雇用契約を一方的に解約するようなケースです。
このような試用期間は日本の会社で広く利用されていますが、その試用期間があまりにも長すぎる場合には労働者が長期間にわたって本採用されるかわからない不安定な立場に置かれることになり不都合な結果となってしまいます。
では、このような試用期間の長さは具体的にどれくらいまで許容されるものなのでしょうか。
また、不当に長い試用期間が設定された場合、具体的にどのように対処すればよいのでしょうか。
不当に長期間の試用期間が設定されている場合、労働者からその試用期間の無効を主張して本採用を強制させることができるのかが問題となります。
試用期間であっても労働契約は有効に成立している
まず、試用期間の長さがどれぐらいまで許容できるのかを考える前提として、そもそも試用期間なる状態がどのような法的な効果を生じさせるのかという点を理解しなければなりませんので簡単に説明しておきます。
この点、試用期間の設定された労働契約(雇用契約)であっても使用者との間に有効に労働契約(雇用契約)が成立している点は普通の労働契約(雇用契約)と変わりません。
試用期間は、その試用期間中に労働者の適性や能力等を観察して本採用しないと判断した場合に使用者に一方的な解雇または本採用の拒否という形で労働契約(雇用契約)を解約する権利が留保されている契約であると解釈されているからです。
試用期間中は、使用者側に試用期間満了時において解雇または本採用拒否によって労働契約(雇用契約)を解除することができる権利が留保されているだけであって、使用者と労働者の間には有効に労働契約(雇用契約)が成立している点は通常の労働契約(雇用契約)と変わらないのです。
ですから、試用期間後の本採用拒否は実質的には解雇と差異はありませんので解雇の有効性を規定した労働契約法第16条に準じて厳格に考えなければなりませんし、試用期間の長さについても解約権が留保された契約が不当に長期に及ばないように抑制的に考えなければならないと言えます。
試用期間の長さはどの程度まで許されるか
このように、試用期間は使用者側に本採用拒否や解雇の権利が留保されているといっても労働者との間に有効に労働契約(雇用契約)が結ばれていることになりますから、本採用が受けられない可能性のある不安定な地位に労働者を置くことになる試用期間の長さは不当に長いものであってはならないと考えなければなりません。
では、その試用期間が具体的にどの程度の長さまで許容されるかという点が問題となりますが、結論から言えば確定的な期間の基準はありません。
あくまでもケースバイケースで考えるしかありませんが、過去の裁判例(ブラザー工業事件(名古屋地裁昭和59年3月23日判決))では、当初の見習い期間(最短で半年、最長で1年から1年3か月)を経過した労働者が、さらに半年から1年の試用期間が設定された試用社員に登用されて試用期間経過後に本採用が受けられなかった事案で、当初の見習い期間が経過し試用社員に登用された時点で本採用がなされたものと認定し、その後の試用期間を公序良俗に反して無効と判断したものがあります。
(前略)…試用期間中の労働者は不安定な地位に置かれるものであるから、労働者の労働能力や勤務態度等についての価値判断を行なうのに必要な合理的範囲を越えた長期の試用期間の定めは公序良俗に反し、その限りにおいて無効であると解するのが相当…(以下略)
※出典:https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/00204.html
この裁判例では、見習社員が雇止めされた例が過去になかったこと、見習社員の募集の際の説明で見習社員が臨時的な雇用だという説明がなされていなかったこと、自己都合退職の事例を除いて見習社員が試用社員や正規の社員に登用される率が極めて高かったこと等を総合的に判断して、その見習い期間を超えた試用期間を公序良俗に反して無効と述べられていますので、この裁判例を根拠に「〇か月以上の試用期間は無効」と言えるものではありません。
しかし、この裁判例は半年間から1年の試用期間(※この裁判例では見習い期間)を設けた後にさらに試用期間を設けたケースで公序良俗違反と認定していますから、試用期間が半年から1年を超えるものは公序良俗に違反する違法性を惹起させる可能性が高いと考えてよさそうです。
ですから、仮に試用期間が半年から1年を超えて設定されている労働契約(雇用契約)において本採用が受けられないというようなトラブルに巻き込まれた場合には、公序良俗に違反する態様がなかったか弁護士などの専門家の助言を受けて検討することも必要になるかもしれません。
試用期間が不当に長い場合の対処法
このように、試用期間が不当に長いケースでは公序良俗違反を理由にその無効を主張することもできますが、実際に勤務している会社で不当に長い試用期間に拘束されている労働者がその無効を主張するのは事実上困難です。
では、そのような場合に労働者は具体的にどのように対処することができるでしょうか。
(1)不当に長い試用期間が公序良俗に違反する旨記載した書面を送付してみる
勤務先の会社が不当に長い試用期間を設定している場合には、その長さが公序良俗に違反する旨記載した書面を作成して会社に郵送してみるというのも対処法の一つとして考えられます。
前述したように、半年から1年を超える試用期間は公序良俗に反して無効と判断される余地がありますが(※必ずしも半年から1年を超える試用期間が無効と言えるわけではありません)、そうした公序良俗に反する余地のある長期の試用期間を設定する会社はそもそも法令遵守意識が低いので口頭でいくら「公序良俗に反する長い試用期間を改めろ」と抗議したとしてもそれが受け入れられる期待は持てません。
しかし、「書面」という形で正式に抗議すれば将来的な訴訟などへの発展を警戒して話し合いや期間の短縮に応じてくる可能性も可能性も少なからずあると思われます。
そのため、こうした場合にはとりあえず書面でその違法性を指摘してみるというのも対処法の一つとして有効な場合があると考えられるのです。
なお、この場合に会社に送付する通知書の文面は以下のようなもので差し支えないと思います。
甲 株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 殿
試用期間が長すぎる件について
私は、〇年〇月〇日に貴社に中途採用として入社し、試用期間を2年とする労働契約の下、現在まで12か月を経過して勤務してきました。
しかしながら、貴社において新卒者の採用においてはこうした試用期間は設けられておりませんから、中途採用者に対してのみ試用期間を2年とする貴社の取り扱いは、労働者の労働能力や勤務態度等についての価値判断を行なうのに必要な合理的範囲を越えたているとしか思えません。
また、すでに私が貴社において1年以上勤務している事実がある以上、その1年の期間中に貴社が私の労働能力や適性を判断することは社会通念に照らして十分に可能であったと考えられますから、2年もの長期にわたって私の労働能力や適性等に就いて判断することに合理性はないようにも思えます(※ブラザー工業事件:名古屋地裁昭和59年3月23日判決参照)。
つきましては、かかる長期間におよぶ試用期間は公序良俗に反し無効とも考えられますので、直ちに当該試用期間の再検討を申し入れいたします。
以上
〇年〇月〇日
〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号○○マンション〇号室
○○ ○○ ㊞
(2)労働局の紛争解決援助の手続きを利用してみる
不当に長期に渡る試用期間を設定されて本採用が受けられない場合には、その事実を労働局に相談(申告)して労働局の紛争解決援助の手続きを利用してみるというのも対処法の一つとして考えられます。
労働局では労働者と事業主の間で発生したトラブルを話し合いで解決させるための紛争解決援助の手続きを用意していますが、長期の試用期間が設定されて本採用が受けられないと言うトラブルもこの手続きの対象となりえます。
この点、この労働局の紛争解決援助の手続きに法的な拘束力はありませんので、会社側が手続きに応じないケースでは解決は望めませんが、会社側が手続きに応じるケースでは会社が労働局から出される助言や指導、あっせん案に従うことで不当に長い試用期間が改善される可能性も期待できます。
そのため、こうした案件でも労働局の紛争解決援助の手続きを利用してみるというのも解決につながる場合があると考えられるのです。
なお、この労働局の手続きについては『労働局の紛争解決援助(助言・指導・あっせん)手続の利用手順』のページで詳しく解説しています。
(3)弁護士に相談する
これら以外の方法としては弁護士に個別に相談して示談交渉や訴訟などを利用して支払いを求める方法が考えられます。
前述したように、試用期間の長さについて公序良俗違反として違法性を指摘できるかはケースバイケースで検討するしかありませんので、(1)の通知書を送付する方法をとるよりも、最初から弁護士(または司法書士)など専門家に相談した方がよいケースも多いかもしれません。
法律の素人が下手に交渉してしまえばかえって不利な状況に陥ってしまう危険性もありますので、上記の方法をとるにしても、事前に弁護士に相談することを考えてもよいでしょう(なお、弁護士への相談は30分5000円程度が相場ですから、実際に事件を依頼するかどうかは別として相談だけしてみるのもよいでしょう)。
(4)その他の対処法
上記以外の方法としては、各都道府県やその労働委員会が主催する”あっせん”の手続きを利用したり、弁護士会や司法書士会が主催するADRを利用したり、裁判所の調停手続きを利用して解決を図る手段もあります。
なお、これらの解決手段については以下のページを参考にしてください。