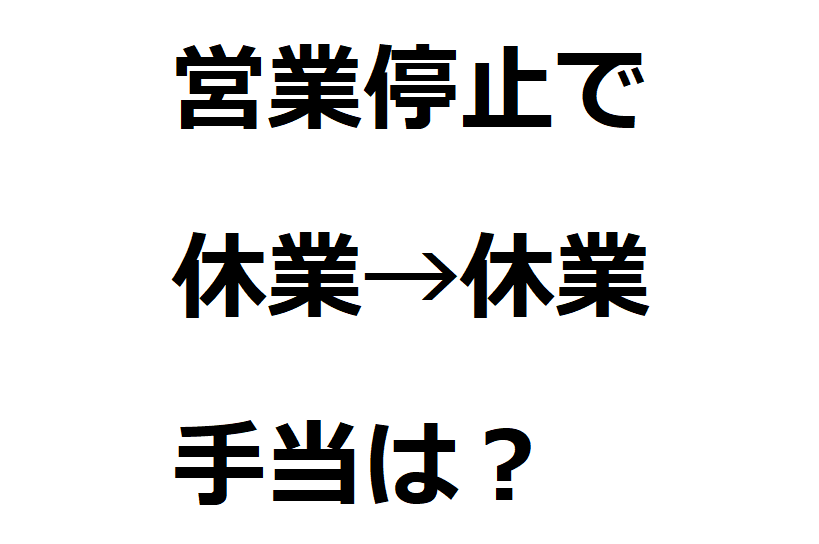監督官庁である行政機関から何らかの行政処分が行われ会社が休業になる場合があります。
たとえば、エステを経営する会社が詐欺的な勧誘で顧客に損害を与え消費者庁から営業停止処分を受けて休業したり、食中毒を起こしたレストランが保健所から営業禁止処分を受けて一定期間アルバイト従業員を休ませるようなケースです。
このような行政機関からの勧告等で会社が業務を停止した場合、労働者は出勤して働くことができなくなりますが、労働者はその会社から支払われる給料で生活を賄っているので休業期間中の賃金や休業手当が支払われないと死活問題となってしまいます。
一方、会社の側としては監督官庁から処分を受けたことに何らかの責められるべき点があったとしても、営業停止という行為自体は会社が自ら望んだものではなく行政機関から強制されて休業しているだけですから、そのようにして行政機関から強制的に休業させられる場合にまで労働者に賃金(または休業手当)を支払わなければならないとなると、働いてもいない労働者にお金を支払うことを強制させられる点で納得できない面もあります。
では、このように監督官庁である行政機関から業務停止処分などを受けたことを理由に会社が休業した場合、労働者はその休業期間中の賃金または休業手当の支払いを請求することができるのでしょうか。
個別の合意があれば行政機関からの業務停止等による休業であっても「賃金」を請求できる
このように、行政機関からの業務停止や営業禁止の処分・勧告等によって会社が休業する場合に労働者が休業期間中の「賃金」の支払いを求めることができるかという点が問題となりますが、この問題は一義的には使用者と労働者の間で「賃金」の支払いに関する合意があるかによって左右されます。
つまり、会社と労働者の間であらかじめ
「監督官庁からの勧告や処分によって休業する場合、会社はその休業期間中の賃金を支払う」
あるいは
「天災事変などの不可抗力による休業の場合を除き、会社はその休業期間中の賃金を支払う」
などという合意が使用者と労働者の間で結ばれている場合には、労働者はたとえ会社が行政機関からの勧告や処分によって休業する場合であっても、会社に対してその休業期間中の「賃金の全額」の支払いを求めることができるということになります。
これは、そのような合意がある場合は、その合意が雇用契約(労働契約)の内容となって契約当事者である会社と労働者を拘束することになるからです。
この点、会社との間に監督官庁からの勧告や処分によって休業する場合の「賃金」の支払いに関する合意があるかないか具体的にどのようにして確認すればよいかが問題となりますが、雇用契約(労働契約)の内容は
- 雇用契約書(労働契約書)
- 労働条件通知書
- 就業規則
- 労働協約
- その他使用者と労働者の間で個別に合意した合意書・同意書等
の規定によって定まることになりますので、入社する際に会社から受け取った、あるいは会社に備え付けられているこれらの書面の内容を確認して判断することが必要になるでしょう。
なお、これらの書面の具体的な確認方法は以下の方法を参考にしてください。
- 雇用契約書(労働契約書)
→雇用契約書または労働条件通知書を作ってくれない会社の対処法 - 労働条件通知書
→雇用契約書または労働条件通知書を作ってくれない会社の対処法 - 就業規則
→会社に就業規則があるかないか確認する方法
→就業規則を見せてくれない会社で就業規則の内容を確認する方法 - 労働協約
→会社の労働組合で確認する - その他会社との間で取り交わした合意書(承諾書や誓約書も含む)
合意がなければ行政機関からの業務停止等による休業期間中の「賃金」は請求できない
このように、監督官庁である行政機関から業務停止や営業禁止の勧告・処分を受けて会社が休業する場合であっても、会社との間でその場合でも「賃金」を支払う旨の合意がある場合には、会社に対してその休業期間中の「賃金」の支払いを請求することが可能です。
では、そのような合意がない場合はどうなるでしょうか。
当事者間で合意がない場合は法律の規定によって判断するしかありませんので、法律の規定を適用して業務停止や営業禁止の勧告・処分を受けて会社が休業する場合に労働者が「賃金」の支払いを請求できないか確認してみましょう。
この点、使用者と労働者の間で結ばれる雇用契約(労働契約)も契約の一つである以上、民法の契約に関する条文が適用されますが、会社が休業した場合における休業期間中の賃金の支払いについては民法第536条2項の危険負担の規定によって判断されるものと考えられています。
【民法第536条2項】
(債務者の危険負担等)
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。(後段省略)
しかし、上に挙げた条文を見てもわかるように民法第536条2項では「債権者の責めに帰すべき事由」によって債務の履行ができない場合に限って債務者の反対給付を受ける権利の行使が認められると規定されていますから、「債権者の責めに帰すべき事由ではない事由」によって債務の履行ができない場合には、債務者は反対給付を受ける権利を行使することができないことになります。
そうすると、これを雇用契約(労働契約)に当てはめた場合には、「会社の責めに帰すべき事由」によって会社が休業する場合に限って労働者はその反対給付請求権となる「賃金」の支払い請求権を行使することができるということになりますから、「会社の責めに帰すべき事由ではない事由」によって休業する場合、つまり「会社の都合によらない事由」で休業する場合には、労働者は会社に対して休業期間中の「賃金」の支払いを請求することができないということになるでしょう。
そうすると、仮に監督官庁である行政機関から業務停止や営業禁止の勧告・処分を受けて会社が休業する場合には、その休業すること自体は会社が望んだものではなく、行政機関から強制されて休業するだけに過ぎませんから、そこに「責めに帰すべき事由」は存在しないといえます。
もちろんその業務停止や営業禁止の処分を受けてしまったそのことについて会社に何らかの責められるべき点はありますが、それは「業務停止や営業禁止の処分を受けたこと」に対する責めに帰すべき事由であって、「休業することになったこと」に対する事由ではないからです。
ですから、監督官庁である行政機関から業務停止や営業停止の処分を受けたことを理由に会社が休業した場合には、その休業した会社に民法第536条2項の「責めに帰すべき事由」はないと判断することができますので、労働者はその休業の場合に民法第536条2項を根拠にして休業期間中の「賃金」の支払いを求めることはできない、という結論になります。
合意がなくても行政機関からの業務停止等による休業期間中の「休業手当」の請求はできる
以上で説明したように、会社との間で行政機関から業務停止等を受けた場合の休業でも「賃金」を支払うことが会社と労働者の間で合意されている場合には労働者はその休業期間中の「賃金」の支払いを求めることができますが、その合意がなされていない場合には、その休業は会社の「責めに帰すべき事由」によるものではないと判断されるため、労働者は民法第536条2項の規定を根拠にして「賃金」の支払いを求めることはできないということになります。
では、「賃金」は請求できないとしても、「休業手当」の支払いを求めることはできないでしょうか。
会社が休業した場合の「休業手当」の支給については労働基準法第26条に規定がありますが、監督官庁である行政機関から業務停止や営業禁止の勧告・処分を受けて会社が休業する場合もその労働基準法第26条の規定に基づいて労働者が会社に対して「休業手当」の支払いを求めることができるのか、という点が問題となります。
【労働基準法第26条】
(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
この点、上に挙げた条文を見てもわかるように、労働基準法第26条では「使用者の責めに帰すべき事由」によって休業する場合についてのみ「休業手当」の支払いが義務付けられていますので、先ほど述べたように会社が行政機関から業務停止等の処分を受けて休業すること場合には、会社が望んで休業するわけではなく監督官庁である行政機関から強制させられて休業するだけに過ぎませんから、その休業すること自体に会社の責めに帰すべき事由がないと判断できる以上、労働基準法第26条の「責めに帰すべき事由」の要件を満たさないので労働者は労働基準法第26条を根拠にして「休業手当」の支払いを求めることはできないとも思えます。
しかし、このような解釈は誤りです。
なぜなら、労働基準法第26条の「責めに帰すべき事由」は、民法第536条2項における「責めに帰すべき事由」よりも広く解釈されており、民法第536条2項の「責めに帰すべき事由」にならないような経営上の障害も天変地異等の不可抗力に該当しない限り、労働基準法第26条の「責めに帰すべき事由」には含まれると考えられているからです(※菅野和夫著「労働法(第8版)」弘文堂232頁参照、参考判例→ノースウエスト航空事件:最高裁昭和62年7月17日|裁判所判例検索)。
民法第536条2項の規定は、債権者の都合によって債務者が債務を履行することができなくなった場合に反対給付を受ける権利が行使できなくなってしまう危険を債権者に負担させ、その債権者と債務者の公平を図る趣旨で規定された条文ですから、行政機関から業務停止等を受けたような会社に直接的な責任のない休業について会社に「賃金」の支払いを強制しなくても労働者に不利益とまでは言えません。会社に直接的な責任のない休業の場合に「賃金」の支払いを強制させる方がかえって契約当事者間の公平を害してしまうからです。
しかし、労働基準法第26条は使用者が休業する場合に平均賃金の6割の休業手当の支給を義務付けることで労働者の最低生活費を担保し労働者の生活を安定させるために規定された条文ですから、使用者に直接的な責任のない休業であっても、それが天災事変などの不可抗力にあたらない限り「責めに帰すべき事由」が「ある」と判断して休業手当の支給を義務付ける方が労働者の保護という趣旨に合致します。
そのため労働基準法第26条の「責めに帰すべき事由」は民法第536条2項の「責めに帰すべき事由」よりも広く解釈する取り扱いが取られているのです。
ですから、監督官庁である行政機関から業務停止や営業禁止の勧告・処分を受けた場合など民法第536条2項の「責めに帰すべき事由」が「ない」と判断される休業であっても、労働基準法第26条の「責めに帰すべき事由」における帰責事由は「ある」と判断されることになりますので、労働者はそのような場合でも労働基準法第26条を根拠にして会社に対して「平均賃金の6割の休業手当」の支払いを求めることができる、という結論になります。
雇用契約書や就業規則で「休業手当」の支給割合が定められている場合はその金額を請求できる
このように、監督官庁である行政機関から業務停止や営業禁止の勧告・処分を受けたことを理由に会社が休業した場合であっても労働者は労働基準法第26条の規定に基づいてその休業期間中の「平均賃金の6割の休業手当」の支払いを請求することができます。
もっとも、その「平均賃金の6割」の部分については個別の雇用契約や就業規則等で別段の定めをすることが認められますので、たとえば
「行政機関からの業務停止等による休業の場合、会社は平均賃金の8割の休業手当を支払う」
あるいは
「天災事変などの不可抗力で休業する場合を除き会社は平均賃金の7割の休業手当を支払う」
などと規定されている場合には、労働者はその「平均賃金の8割」または「平均賃金の7割」の休業手当の支払いを求めることができます。
ですから、仮に監督官庁である行政機関から業務停止や営業禁止の勧告・処分を受けたことを理由に会社が休業する場合には、入社する際に交付を受けた雇用契約書(労働契約書)や労働条件通知書あるいは会社の就業規則や労働協約にそのような規定がないか確認することが必要となります。
なお、この場合でも労働基準法第26条の規定を下回る割合で合意することはできませんので、たとえば
「行政機関からの業務停止等による休業の場合、会社は平均賃金の5割の休業手当を支払う」
などとそれらの書類に規定されている場合にはその「平均賃金の5割」という部分が労働基準法第26条の基準に満たないため無効と判断されることになりますから、そのようなケースでは労働者は会社に対して「平均賃金の6割」の休業手当の支払いを求めたり、または既に受領した「平均賃金の5割」の金額と「平均賃金の6割」の金額との差額を会社に対して請求することができるということになります。