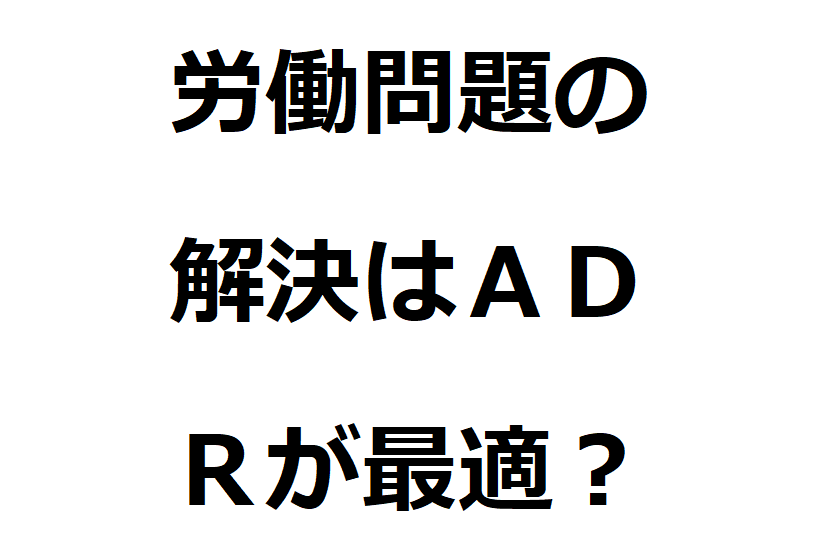労働問題の解決方法としては、労働基準監督署への労働基準法違反の申告や労働局の紛争解決援助の手続き、あるいは弁護士や司法書士に裁判を依頼するなど様々な方法がありますが、それら以外で意外と労働トラブルの解決に使えそうなのが「ADR」という手続きです。
ADRとは「Alternative Dispute Resolution」の略称で、日本語では「裁判外紛争解決手続き」と説明されますが、要は「法的なトラブルを裁判以外の話し合いによって解決しよう」という手続きのことをいいます。
具体的には弁護士会や司法書士会が主催しているものが代表的で、何らかの法的なトラブルが発生した場合に、紛争当事者の一方又は双方が弁護士会や司法書士会にADRの申し立てを行い、弁護士や司法書士に当事者の間に立ってトラブル解消に向けた話し合いの仲裁を行ってもらう手続きのことになります。
たとえば、「AさんがBさんにお金を貸したのにBさんがお金を返してくれない」といったトラブルを解決するため弁護士会のADRを利用した場合であれば、AさんがADRの手続きを実施する弁護士会にADRの申請を行うと、弁護士会からBさんにADRへの参加を呼び掛ける通知を行われ、Bさんから「ADRに参加してもいいですよ」という回答を得られれば弁護士会館などの一室にAさんとBさんが出向き、弁護士の同席のもとでAさんとBさんの間で「お金を返すか返さないか」という話し合いがなされることになります。
労働問題の解決手続きとしてADRを勧めることができる3つの理由(ADRのメリット)
労働問題の解決手段としてADRの手続きをおススメできる理由はいくつかありますが、主な理由としては次の3つが挙げられます。
(1)会社側との対立を最小限に抑えることができる
労働問題の解決手段としてADRが適していると考えられる理由の一つ目は、裁判所における裁判や労働局の”あっせん”などの手続きと比較して、会社(個人事業主も含む)側との対立がそれほど深刻化しないで済むという点が挙げられます。
なぜなら、裁判や労働局の手続きを利用する場合は「大人のケンカ」をすることになるため会社側の心証は限りなくゼロになるまで悪化しますが、ADRの手続きは単に紛争の相手方と「話し合い」をするだけの手続きであるため会社側の心証もそこまでは悪くならないと考えられるからです。
労働問題の解決手段として裁判所における裁判手続きを利用した場合、結果的に会社側を「被告」として裁判所に強制的に引きずり出し、裁判官の面前で会社側の違法行為を指摘ないし糾弾しなければならないことになりますので、会社側におけるその労働者に対する心証は悪くなります。
また、労働局の紛争解決援助の手続きを利用して労働局からの”助言”や”指導”を求めたり”あっせん”の手続きを利用する場合も、会社側は労働局から出頭を求められたり一定の勧告等を受けることになるわけですから、労働局という本来は忌避したい行政機関への対応を迫られる限りにおいて、会社側にとっては相当なストレスになる結果、それを招いた労働者への心証は悪くなるでしょう。
裁判や労働局の手続きを利用して労働問題を解決する場合には、会社側と「大人のケンカ」をすることになるわけですから、たとえ会社側に法的・道義的な非があり、労働者側に歴然とした正義があったとしても、会社側からは反抗的な労働者というレッテルを張られてしまうことは避けられないわけです。
しかし、労働問題の多くは、その問題が解決した後もその会社で働き続けるケースが圧倒的に多いわけですから、裁判や労働局の手続きを利用して問題が解決したとしても、その後の就労に影響するような会社側の心証を悪くする行為はできるだけ避ける方がよいケースも多いのが現実です。
この点、ADRの手続きを利用する場合はこのような会社側の心証を損ねることは最小限に抑えることができます。
先ほども説明したように、ADRの手続きは使用者(雇い主)に対して弁護士会や司法書士会で行われる「話し合い」に出席を求めるだけで「ケンカ」をするわけではありませんから、ADRへの参加を求められる会社側としてもそれほど労働者に対する心証が悪くなることはないからです。
ADRの手続きは裁判所や労働局など「公的」な機関が関与するものではなく、あくまでも私的な団体に過ぎない弁護士会や司法書士会の手続きですから協力するかしないかはもっぱら会社側の自由意思に委ねられますし、裁判所や労働局といったある種の権威的な場所への出廷を求められる場合と比較して、一私人の団体に過ぎない弁護士会や司法書士会の会議室に出向くことは会社側が受けるストレスも相当程度低くなります。
このように、ADRの手続きは紛争の相手方にとってもそれほど負担にならないのが通常ですので、問題解決後もその会社で働くことが前提となるケースの多い労働問題に関するトラブルの解決手段としては、より適しているといえます。
(2)会社側に言いくるめられてしまう心配がない
労働問題の解決手段としてADRを利用するメリットの2つ目は、法律的に誤った内容で会社側にいいように言いくるめられてしまう心配がないという点です。
先ほども説明したように、弁護士会や司法書士会が主催するADRの手続きでは労働法に精通した弁護士や司法書士が会社側との話し合いの場に同席してくれることになりますので、仮に話し合いの途中で会社の担当者が法律や判例の見解に反する主張を行ったとしても、同席している弁護士や司法書士が「その意見は法律解釈として間違ってますよ」とか「その見解は判例の見解からかけ離れていますよ」などと助言をしてくれます。
ADRの手続きは「当事者間の話し合い」ではあっても、法律や判例の見解に準拠した話し合いがなされることが担保されていますから、通常の示談交渉の場であれば交渉力の優る会社の担当者であっても、ADRの手続きにおいては無暗に法律や判例の見解に反する主張はできないわけです。
ADRでは、弁護士や司法書士からその発言の法的適合性がチェックされることになりますから、法知識や交渉力の乏しい一般の労働者であっても安心して交渉に臨めることが可能です。
(3)費用が安い
労働問題の解決手段としてADRの利用が勧められる3つ目の理由は、なんといってもその費用の安さです。
もちろん、労働局の紛争解決援助の手続き(あっせんも含む)を利用する場合は費用が一切かかりませんので労働局の手続きと比較すれば経済的な負担はありますが、ADRは1つの紛争について数千円から数万円程度の費用負担(※ADR費用は同席する弁護士やへの報酬や話し合いの会場の使用料となります)で利用することができますので、経済的な負担はそれほど重くありません。
裁判を行う場合は訴訟費用だけでも数万円、弁護士や司法書士を雇うとなれば着手金や成功報酬も数万円から数十万円必要になる場合もありますから、それに比べると格段に安く労働問題の解決を解決を図ることができます。
労働問題の解決手段としてADRを利用する場合に生じるデメリット
以上のように、労働問題の解決手段としてADRを利用するメリットをいくつか挙げることができますが、ADRも万能な手続きではないため、次のようなデメリットも存在します。
(1)会社側がADRへの参加を拒否する場合は解決できない
労働問題の解決手段としてADRを利用する場合の最大のデメリットは、会社側がADRへの参加を拒否する場合にはADRの手続き自体利用できないという点です。
先ほども説明したように、ADRの手続きは弁護士会や司法書士会という私的な資格者団体が「話し合い」のテーブルを用意するだけの手続きにすぎませんから、ADRの参加を打診された会社側は参加を拒否することも全くの自由です。
会社側がADRへの参加を拒否しても会社側に何らのペナルティーも課されませんし、労働者側も会社の担当者や経営者に対してADRへの出席を強制することはできませんから、ADRでの労働問題解決は、もっぱら会社側のADR手続きへの協力意思の有無に左右されることになります。
会社側が「ADRには参加しない」と回答する場合はADRの手続き自体が利用できませんので、問題解決に協力的でない会社が相手となる場合にはADRの手続きは労働問題解決の手段としては適当ではないといえます。
(2)会社側がADRで合意した内容を反故にする場合は解決できない
労働問題の解決手段としてADRを利用する場合のデメリットの2つ目は、ADRの話し合いで合意した内容の実現には強制力がないという点です。
労働問題を裁判所の裁判で解決する場合には、裁判所から出される「判決」であったり、裁判上の和解手続きにおける「和解」が裁判所から出されますが、その判決書や和解書の内容は裁判上の強制力を含みますので、その裁判所の判決なり和解した内容を被告である会社側が実現しない場合には、強制執行を行った強制的に実現させることも可能です。
たとえば「未払いの残業代を支払え!」と請求する裁判であれば、判決や訴訟上の和解がなされて裁判所から「会社は〇円の残業代を支払いなさい」というような内容の判決書や和解調書が出されれば、たとえその判決書のとおりに会社が残業代を支払わなかったとしても、その裁判所から出された判決書や和解調書を裁判所に提出することで強制執行の手続きを行い、会社の利用する銀行口座などを差し押さえて強制的に未払い残業代を徴収することも可能です。
しかし、ADRの場合にはそうはいきません。ADRの手続きは弁護士会や司法書士会などあくまでも私的な団体が主催する「話し合い」にすぎませんので、ADRの話し合いの場で合意した内容を強制的に実現させることができないからです。
たとえば「未払いの残業代を支払え!」という内容で弁護士会のADRを利用し会社側がそのADRへの参加を承諾して話し合いの結果「会社は〇円の残業代を〇日までに支払います」という合意書に会社側がサインしたとしても、その合意書のとおりに会社側が未払い残業代を支払わない場合には、それ以上労働者は残業代の支払いを強制させることはできません。
このようなケースでは労働者は改めて裁判などを提起して未払い残業代を回収しなければならないので、ADRの合意を反故にするような不誠実な会社が相手となるケースでは、ADRを利用すること自体が無駄になってしまうでしょう。
ADRで解決するのに適した労働問題とは?
以上のように、ADRの手続きは労働問題の解決に適した手続きといえる面があるものの、手続きへの参加やADRで合意した内容に強制力がないことから、トラブルのケースによっては適切な解決手段にはなりえない場合もあるといえます。
そうすると、どのような労働問題でADRの手続きがトラブル解消に向けた手続きとして適しているといえるのかという点が問題となりますが、具体的には次の2つの要件をすべて満たすような事案ではADRを利用しても十分に労働問題の解決が図れるのではないかと思います。
(1)会社側が話し合いに応じてくれる程度に協力的な事案
会社側が話し合いでの解決に応じてくれそうな労働問題の案件では、ADRを利用して問題の解決を図ることも十分に見込めると思います。
先ほども述べたように、ADRの手続きには参加への強制力や合意した内容に関する強制力がありませんから、話し合いでの解決に最初から否定的な会社が相手だと、ADRの手続きを進めること自体困難です。
しかし、会社側がある程度話し合いに応じる姿勢を示している場合はADRの手続きで話し合いで解決できる蓋然性は高いといえますから、労働局や裁判所の手続きではなくADRの手続きを利用してみるのも解決方法としては有効に機能すると思います。
また、会社側が話し合いに応じる姿勢を示しているにもかかわらず労働局の紛争解決援助の手続きや裁判所の裁判手続きを利用してしまうと、協力的な会社の姿勢を硬化させてかえって問題解決を困難にしてしまう可能性もありますので、会社側がある程度協力的な態度をとっている場合には、最初から労働局や裁判所に訴えたりするのではなく、まず最初に会社側の負担が少ないADRの手続きを利用して話し合いで解決を図るのも労働問題解決の戦術としては悪くないと思います。
(2)会社側がADRの合意内容を遵守する程度に常識的な事案
また、(1)に加えて、会社側がADRの話し合いで合意した内容に従う程度に常識的な会社であることもADRを利用するうえで重要な判断基準となります。
先ほども説明したように、ADRの話し合いで合意した内容は合意書にサインを求めることで会社側に実現を促すことができますが、その合意自体に強制力はないので会社側がそのADRの合意を反故にする場合はADRの手続きでは問題の解決を図ることはできなくなります。
話し合いで合意した内容を反故にするような非常識な会社であったり、最初から合意を無視する気満々でADRに参加するようなブラック体質を持った会社が相手だとADRの手続きを利用すること自体無意味となるわけです。
ですから、ADRの手続きで労働問題を解決しようとする場合は、その相手方となる会社(個人事業主も含む)がADRでの合意内容に従う程度に常識的な会社であることは必須となります。
労働問題の相手方となる会社(個人事業主も含む)が、話し合いで合意した内容を反故にすることがあらかじめ予測できるような悪質な会社である場合には、ADRの手続きではなく最初から裁判などでの解決を図る方がよいと思います。
ADRの利用手順
ADRを利用したい場合は、最寄りの弁護士会や司法書士会に電話などで連絡し「ADRの手続きを利用したいこと」を伝えてください。
後は弁護士会や司法書士会の方でADRの利用手順の詳しい説明や申し込み方法を丁寧に教えてくれると思いますので、詳しい話を聞いたうえで実際に利用するかしないか最終的に判断すればよいと思います。
なお、弁護士会や司法書士会の主催するADRの利用方法等については弁護士連合会や司法書士会連合会のこちらのサイトでご確認ください。
日本弁護士連合会│法律相談
日本司法書士会連合会 | 話し合いによる法律トラブルの解決(ADR)