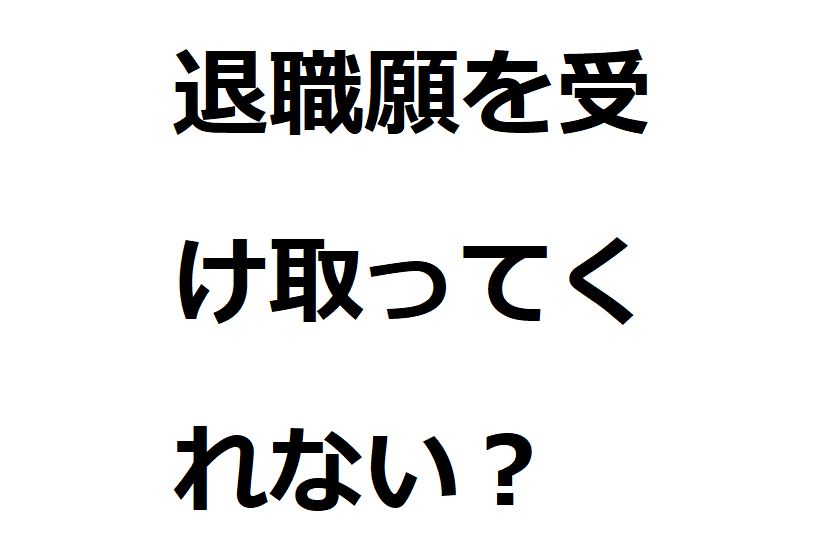勤務先の会社を辞める場合、退職届(退職願)を上司などに提出し退職の意思表示を行うのが通常ですが、ブラック体質のある会社などでは会社側が退職届(退職願)の受け取りを拒否し、事実上労働者の退職を妨害するケースが見受けられます。
このように会社側から退職届(退職願)の受け取りを拒否された場合、仕事を辞めることができないのでしょうか?
使用者(雇い主)が労働者の退職の意思表示を拒否することが法的に認められるのか、また、実際に退職届(退職願)の受け取りを拒否されて退職を拒否された場合の具体的な対処法が問題となります。
使用者(雇い主)は労働者からの退職の意思表示を拒否することができない
結論から言うと、使用者(雇い主)は労働者からの退職の意思表示を拒否することは法律上認められていませんから、使用者(雇い主)が労働者から提出された退職届(退職願)の受け取りを拒否することはできません。
仮に、使用者が労働者から提出を受けた退職届(退職願)の受け取りを”事実上”拒否したとしても、その労働者が「退職した」という効果は法律上有効に成立することになりますので、”法律上”は労働者からの退職の意思表示を拒否することはできないということになります。
ではなぜ、このような結論になるかというと、労働者が使用者(雇い主)に対して「退職する」と伝える行為は「意思表示」の問題に過ぎないからです。
労働者が会社を辞める場合、口頭で「退職します」と上司や経営者に告知するか、「退職届(退職願)」といった書面を作成して退職の申入れをすることが必要となりますが、それは「雇用契約を解約する」という一方的な通知であり、法律上は意思表示にすぎません。
【民法97条】
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
この点、意思表示はその相手方に到達した時からその効力が生じるわけですから、退職の申入れも「雇用契約を解約する」という意思表示である以上、会社における退職届(退職願)の受領権限のある者に到達した時点で無条件にその退職の効果が生じることになります。
そうすると、いったん退職届(退職願)を提出するなどして退職の意思表示を行えば、その後でいくら会社側がその受け取りを拒否したり送り返してきたとしても、すでに退職の意思表示が相手方に「到達」したという事実が覆ることはないことになります。
ですから、会社側は、いったん労働者が退職届(退職願)を提出するなどして退職の意思表示を行った後は、いかなる主張をもってしてもその退職を申し出た労働者の退職を拒否することはできないのです。
労働者が法律や契約に違反して辞める場合も使用者は退職の意思表示を拒否することはできない
以上のように、労働者が退職を申し入れる行為は「雇用契約を解約する」という意思表示にすぎませんので、その意思表示がいったんなされ会社側に到達した場合には、もはや使用者はそれを拒否することはできないということになります。
なお、この理屈は仮に労働者が法律や契約(雇用契約)に違反して法律上または契約上の根拠なく退職する場合であっても同じです。
なぜなら、たとえ法律の規定に反して労働者が退職する場合であっても、それは単に「雇用契約に違反する」という債務不履行責任(民法415条)を生じさせるにとどまり、その退職という法律上の効果まで否定されるわけではないからです。
たとえば「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」で働く労働者は「退職日の2週間前までに退職の意思表示をすること」が民法627条1項で求められますし、「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約」で働く労働者は「やむを得ない事由」がある場合(民法628条)か「契約期間の初日から1年が経過」した場合(労働基準法137条)でなければ契約期間の途中で退職することが認められていませんので、労働者がこれらの規定に違反して退職する場合には「雇用契約違反」として損害賠償責任が生じる余地がありますが、労働者がいったん退職届(退職願)を提出するなどして退職の意思表示を行えば、その意思表示が会社側に到達した時点で有効に退職の効果は生じますので、労働者は会社から損害賠償請求される可能性はあっても、会社を退職すること自体は妨げられないということになるわけです。
なお、この点については以下のページでさらに詳しく解説しています。
- 期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)の場合→2週間前に退職届を出さない社員の退職を会社が拒否できない理由
- 期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)の場合→バイト・契約社員の契約違反による退職を会社が拒否できない理由
退職届(退職願)の受け取りを拒否されて退職を妨害された場合の対処法
以上のように、労働者には「退職の自由」が認められており、退職を申し入れるという行為は意思表示の問題にすぎませんから、労働者がいったん退職届(退職願)を提出するなどして退職の意思表示を行った後は、使用者(雇い主)が労働者から提示された退職届(退職願)の受け取りを拒否するなど労働者からの退職の意思表示を拒否することは”法律上”できませんし、仮に”事実上”その意思表示を拒否したとしても、労働者が「退職の意思表示を行った」という法律上の効果は有効に成立するため、労働者の退職は制限されないことになります。
もっとも、そうはいっても会社によっては退職届(退職願)の受け取りを拒否して執拗に就労を強要するケースも見られますので、そのような場合に具体的にどのように対処すればよいのかといった点が問題となります。
(1)郵送で退職届(退職願)を送り付ける
使用者(雇い主)側が退職届(退職願)の受け取りを拒否するような場合は、作成した退職届(退職願)を郵送で会社に送り付けて退職の効力が発生した日以降は出社しないようにするのも一つの対処法として有効です。
退職は「退職します」と口頭で通知するか、もしくは退職届(退職願)を提出し、その意思表示が受理権限のある者に到達した時点で有効に成立しますので、仮に退職届(退職願)の受け取りを拒否されたとしても退職の効果は法律上有効に発生することになります。
しかし、後に裁判になった場合に会社側が「退職届(退職願)は受け取っていない」などと反論してきた場合は労働者側で「退職届(退職願)を提出した」ということを立証しなければなりませんから、会社側が退職届(退職願)の受け取りを拒否しているようなケースでは「退職届(退職願)を提出した」という事実の証拠が残らない”手渡し”よりも、客観的な証拠の残る”郵送”で送付しておく方が無難です。
そのため、客観的な証拠が残るよう、提出する退職届(退職願)のコピーを取ったうえで特定記録郵便など「配達された」という記録が残される郵送方法で送付することが必要なのです。
もっとも、将来的に裁判に発展することが確実なケースでは内容証明郵便で退職届(退職願)を送り付ける方が無難かもしれません。
ただし、先ほど説明したように、「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」の場合に2週間の予告期間を置かなかったり、「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」の場合に「やむを得ない事由」が「無」く「契約期間の初日から1年が経過」していないのに契約期間の途中で退職する場合は、その退職によって使用者(雇い主)に損害が発生した場合に債務不履行(民法415条)や不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求を受けてしまう可能性がありますのでその点には注意が必要です。
なお、実際に使用者(雇い主)に提出する退職届(退職願)は以下のようなもので差し支えありません。
【退職届(退職願)の記載例】
株式会社○○
代表取締役○○ ○○ 殿
退職届
私は、一身上の都合により、△年△月△日をもって退職いたします。
以上
〇年〇月〇日
東京都〇区○○一丁目〇番〇号
○○ ○○ ㊞
なお、内容証明郵便で送る場合は以下のような文面を利用してください。
【退職届(退職願)の記載例※内容証明で送る場合】
退職届
私は、一身上の都合により、△年△月△日をもって退職いたします。
以上
○年○月○日
通知人
東京都〇区〇丁目〇番〇号
○○ ○○
被通知人
東京都〇区〇丁目〇番〇号
株式会社○○
代表取締役 ○○ ○○
(2)労働基準監督署に対して労働基準法違反の申告を行う
(1)の退職届(退職願)を提出しても会社が退職を認めず自宅に押し掛けるなどして就労や復職を強要する場合には、労働基準監督署に労働基準法違反の申告を行うことも考えてよいかもしれません。
先ほども説明したように、退職は雇用契約を解約するという「一方的な意思表示の通知」にすぎませんから、会社がその受け取りを拒否するような場合には内容証明郵便で送り付けて「会社に退職の意思表示が到達した」という事実を作り出すことで法律上の問題は解決しますが、それでもなお会社の役職者等が就労を強要するような場合には、労働者を精神的に追い詰める方法を用いて就労を強要ないし復職を強制しているということになるでしょう。
この点、労働基準法の5条では以下のように使用者(雇い主)が労働者を強制的に就労させる行為が労働基準法違反の行為として禁止されていますから、仮にそのような状況があるとすれば、その会社の労働基準法違反を労働基準監督署に申告することも可能です(労働基準法104条1項)。
【労働基準法第5条】
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
仮に、労働者が労働基準監督署に労働基準法違反の申告を行い、監督署から勧告等が出されれば、会社の方でも退職届(退職願)の受け取りを拒否して退職の効果を否定し就労や復職を強要することを止める可能性もありますので、退職届(退職願)を提出した後も会社側が退職を拒絶し就労を強要する場合には労働基準監督署への申告も考えた方がよいのではないかと思います。
なお、この場合に労働基準監督署に提出する労基法違反の申告書は、以下のような文面で差し支えないと思います。
【労働基準法104条1項に基づく労基法違反に関する申告書の記載例】
労働基準法違反に関する申告書
(労働基準法第104条1項に基づく)
○年〇月〇日
○○ 労働基準監督署長 殿
申告者
郵便〒:***-****
住 所:東京都〇〇区○○一丁目〇番〇号○○マンション〇号室
氏 名:申告 太郎
電 話:080-****-****
違反者
郵便〒:***-****
所在地:東京都〇区〇丁目〇番〇号
名 称:株式会社○○
代表者:代表取締役 ○○ ○○
申告者と違反者の関係
入社日:〇年〇月〇日
契 約:期間の定めのない雇用契約
役 職:特になし
職 種:製造
労働基準法第104条1項に基づく申告
申告者は、違反者における下記労働基準法等に違反する行為につき、適切な調査及び監督権限の行使を求めます。
記
関係する労働基準法等の条項等
労働基準法第5条
違反者が労働基準法等に違反する具体的な事実等
・申告者は〇年〇月〇日に上司である◆◆に2週間後の◇月◇日をもって「一身上の都合」により退職する旨記載した退職届を提出したが、違反者は申告者の退職届の受け取りを拒否した。
・申告者は当該上司に対し法律(民法627条)で労働者に退職の自由が認められていること、退職の意思表示を行った後も就労を強要する場合は強制労働の禁止を規定した労働基準法5条の規定にも違反する可能性があることなどを説明し理解を求めたが、違反者は「今は繁忙期で猫の手も借りたいんだから退職が認められるわけないだろう」の一点張りで退職を認めようとしない。
・そのため申告者は〇年〇月〇日付けで作成した退職届を特定記録郵便で違反者に送付し(当該退職届は同年〇月〇日に違反者に配達されている)退職希望日の◇月◇日以降、出社しないようにしたが、違反者は申告者の自宅に押し掛けるなどしていまだに復職を迫っている。
添付書類等
1.〇年〇月〇日に上司の◆◆に提出した退職届の写し 1通
2.〇年〇月〇日付けで特定記録郵便で送付した退職届の写し 1通
備考
特になし。
以上
※会社側に労働基準監督署に法律違反の申告をしたことを知られたくない場合は「備考」の欄に「本件申告をしたことが違反者に知れると更なる被害を受ける恐れがあるため違反者には申告者の氏名等を公表しないよう求める。」の一文を挿入してください。
(3)その他の対処法
以上の方法でも解決しない場合には、労働局に紛争解決援助の申し立てを行ったり、自治体や労働委員会の「あっせん」を利用したり、弁護士会と司法書士会が主催するADRを利用することも検討する必要があります。
また、案件によっては弁護士や司法書士に個別に依頼して裁判手続きで解決を図る必要がありますので、自力での解決が困難であることがわかった時点で早めに弁護士や司法書士に相談するよう心掛けてください。
なお、これらの対処法を取る場合の具体的な相談場所等についてはこちらのページでまとめていますので参考にしてください。