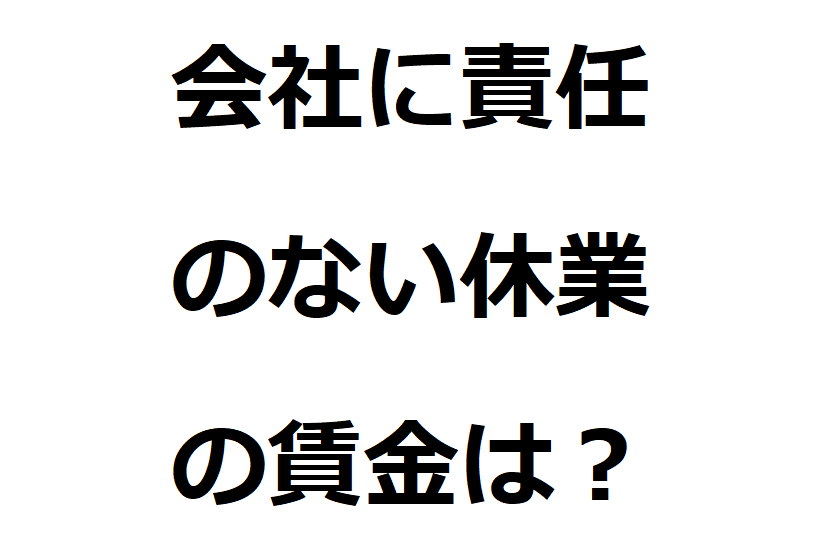会社の都合で休業が発生した場合、労働者は民法第536条2項の規定に従ってその休業期間中の賃金の全額の支払いを会社に対して請求できるのが原則です(※詳細は→会社都合の休業で会社に請求できる給料の金額はいくらか)。
この点、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合に平均賃金の6割の休業手当を支払うことを義務付けた労働基準法第26条との関係が問題となりますが、労働基準法第26条の規定は会社都合の休業の場合に平均賃金の6割の休業手当の支給を罰則をもって強制することで労働者の生活を保障する趣旨で規定されたものに過ぎず、民法第536条2項において生じる使用者の責任(危険負担)を軽減するためのものではありません(ノースウエスト航空事件:最高裁昭和62年7月17日|裁判所判例検索)。
つまり、会社都合の休業が発生した場合、会社は平均賃金の6割の休業手当を支払えば労働基準法違反として刑事罰(労働基準法120条で30万円以下の罰金)から逃れることができますが、労働者に対する賃金全額の支払い義務からは逃れることができないということになります。
そのため、会社都合の休業の場合には、労働基準法第26条の規定を考えたとしても、労働者は会社に対してその休業期間中の賃金の全額の支払いを請求できることになり、会社が平均賃金の6割の休業手当しか支払わない場合には、その支払われた”平均賃金の6割の休業手当”と”賃金の全額”の差額を会社に対して請求することができるということになるのです。
ところで、ここで疑問が生じるのが、「会社都合によらない休業(会社に責任のない休業)」が発生した場合はその休業期間中の休業手当を請求できないのか、という点です。
今説明したように、労働基準法の第26条では「使用者の責めに帰すべき事由による休業」の場合に平均賃金の6割の休業手当の支給を使用者に義務付けていますが、その趣旨は平均賃金の6割の休業手当の支給を罰則(労働基準法第120条で30万円以下の罰金)をもって義務付けることで労働者の生活を保障するところにあります。
しかし、これは何も「使用者の責めに帰すべき事由による休業」が発生した場合に限ったものではありません。仮に「使用者の責めに帰すべきものではない事由」によって休業が発生した場合であっても、その休業期間中の休業手当の支払いが受けられなくなれば労働者の生活は保障されなくなるのは同じだからです。
そうであれば、仮に「使用者の責めに帰すべきものでない事由」つまり「会社の都合ではない事由」によって休業が発生した場合であっても、労働者は会社に対して平均賃金の6割の休業手当を請求することができると考えてもよいような気もします。
では、このように「使用者の責めに帰すべきではない事由」によって休業が発生した場合、労働者はその休業期間中の賃金(または休業手当)の支払いを使用者に対して請求することができるのでしょうか?
「使用者の責めに帰すべきものではない事由」による休業の場合でも、労働者は平均賃金の6割の休業手当の支払いを請求できる
このように、「使用者の責めに帰すべきではない事由」で、つまり「会社の都合によらない事由」で会社が休業した場合にその休業期間中の賃金(または休業手当)を請求することができるのかという点が問題となりますが、この点を考える場合には民法第536条2項を適用して休業期間中の「賃金」を請求することができるのかという論点と、労働基準法第26条の規定を適用して休業期間中の「休業手当」を請求することができるのかという論点に分けて考える必要がありますので、以下それぞれ別に検討してみることにいたします。
(1)「会社の都合によらない休業」において休業期間中の「賃金」を請求することはできない
まず、「会社の都合によらない休業(会社の責めに帰すべきではない事由による休業)」の場合に休業期間中の「賃金」を請求することができるかという点を検討してみますが、結論から言うとこれはできません。
なぜなら、『会社都合の休業で会社に請求できる給料の金額はいくらか』のページでも説明したように、民法第536条2項の規定は債権者の「責めに帰すべき事由」によって債務者が履行不能になった場合に反対給付を受ける権利を失わないことを規定した条文であり、債権者が「責めに帰すべきではない事由」によって生じた債務者の危険までを債権者に負担させる趣旨の規定ではないからです。
【民法第536条2項】
(債務者の危険負担等)
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。(後段省略)
『会社都合の休業で会社に請求できる給料の金額はいくらか』のページでも解説したように、「会社都合による休業」が生じた場合には、民法第536条2項の規定を適用して労働者はその反対給付である休業期間中の賃金を請求する権利を失わないことになるため、労働者は会社都合による休業における休業期間中の賃金の「全額」を会社に対して請求することができました。
しかし、これはその休業が「会社の都合による休業」、つまり「会社の責めに帰すべき事由」によって生じたものであるからこそ民法第536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」に当てはめることで民法第536条2項を適用しそのような解釈が導き出されたものですから、「会社の都合によらない休業」の場合にまで民法第536条2項を適用することはできません。
ですから、仮に「会社の都合によらない休業」が発生した場合には、労働者は会社に対してその休業期間中の「賃金」の支払いを請求することはできないということになります(※ただし、後述するように就業規則や個別の労働契約等で別段定めがあればそれに従うことになります)。
(2)「会社の都合によらない休業」において休業期間中の「平均賃金の6割の休業手当」を請求することはできる
では、「会社の都合によらない休業(会社の責めに帰すべきではない事由による休業)」の場合に、会社に対してその休業期間中の「休業手当」を請求することができるでしょうか。
この点、「会社都合による休業(会社の責めに帰すべき事由による休業)」の場合には、労働者はその労働基準法第26条の規定によって会社に対してその休業期間中の「休業手当」を請求することができましたので(※詳細は→会社都合の休業で会社に請求できる給料の金額はいくらか)、この労基法26条が「会社の都合によらない休業」の場合にも適用できるのかが問題となります。
【労働基準法第26条】
(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
しかし、この条文を見てもわかるように、労働基準法第26条は「使用者の責めに帰すべき事由による休業」の場合に休業手当の支払いを義務付けているだけで、「使用者の責めに帰すべき事由によらない休業」つまり「会社の都合によらない休業」の場合まで休業手当の支払いを義務付けているとは読み取れません。
そのため、労働基準法第26条をそのまま文章どおり読む場合は「会社の都合によらない休業」の場合に労働者は会社に対してその休業期間中の休業手当を請求することができないように思えます。
もっとも、これは労働基準法第26条の解釈として正しくありません。なぜなら、労働基準法第26条の「使用者の責めに帰すべき事由」は、民法第536条2項における「債権者の責めに帰すべき事由」よりも広く解釈されており、民法第536条2項の「使用者の責めに帰すべき事由」にならないような経営上の障害も天変地異等の不可抗力に該当しない限り、労働基準法第26条の「使用者の責めに帰すべき事由」には含まれると解釈されているからです(※菅野和夫著「労働法(第8版)」弘文堂232頁参照、参考判例→ノースウエスト航空事件:最高裁昭和62年7月17日|裁判所判例検索)。
先ほどの(1)で説明したように、民法第536条2項は「債権者の責めに帰すべき事由」における債務者の反対給付請求権の喪失にかかる危険負担を債権者に転嫁して債務者を保護する趣旨のものですから、「会社の都合によらない休業」の場合にまで同条項の適用を拡大させなければならない合理的な理由はないので、「会社の都合によらない休業」の場合に休業期間中の賃金の請求を否定しても労働者にとって不測の不利益が生じるとまでは言えません。
一方、労働基準法第26条はそもそも会社都合の休業の場合に平均賃金の6割の休業手当の支払いを義務付けることで労働者の生活を保護するためのものですから、民法第536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」には含まれない経営上の障害等によって生じた休業も「使用者の責めに帰すべき事由」に含めて解釈する方が労働者の生活の保護という休業手当の趣旨に合致します。
そうであれば、たとえ「使用者の責めに帰すべき事由によらない休業」つまり「会社の都合によらない休業」の場合であってもそれが経営上の障害等に含まれる事情によって生じた休業の場合には、会社にその休業期間中の休業手当の支払いを義務付けるべきであるといえます。
このような理由から、法律的な考え方(通説・判例の見解)では、「会社の都合によらない休業」の場合にも労働基準法第26条の「使用者の責めに帰すべき事由」に含まれるものと判断して、使用者に対して休業期間中の「休業手当」の支払いを認める取り扱いが取られています。
つまり、「会社の都合によらない休業」が発生した場合には、会社に対して民法第536条2項を根拠にしてその休業期間中の「賃金」の支払いを請求することはできませんが、労働基準法第26条の規定を根拠にして、その休業期間中の「平均賃金の6割」に相当する「休業手当」の支払いを請求することはできる、ということになるのです。
「会社の都合によらない休業」とは具体的にどのような場合か
以上で説明したように、仮に「会社の都合によらない休業」が発生した場合であっても、労働者は労働基準法第26条の規定を根拠にして、その休業期間中の「休業手当」の支払いを請求することは可能と言えます。
もっとも、だからといって「会社の都合によらない休業」の場合のすべてに会社に対して労働基準法第26条の規定に基づく休業手当の支払いを請求できるわけではありません。
なぜなら、先ほど説明したように労働基準法第26条の趣旨は平均賃金の6割の休業手当の支払いを会社に義務付けることで労働者の生活を保障するところにありますが、天災事変などの不可抗力によって生じた休業の場合にまで会社に休業手当の支払いを義務付けるのは、会社に対してあまりにも公平性を欠く結果となってしまうからです。
この点、「会社の都合によらない休業」の場合にどの程度の範囲まで労働基準法第26条の適用が認められるかが問題となりますが、法律的には
「使用者の帰責事由とならない経営上の障害も天災事変などの不可抗力に該当しない限りはそれに含まれる」
※出典:菅野和夫著「労働法(第8版)」弘文堂232頁より引用
と解釈されています。
つまり、天災事変などの不可抗力によって会社が休業した場合には、労働者は会社に対して労働基準法第26条の適用を主張してその休業期間中の休業手当の支払いを請求することは基本的にできませんが、「経営上の障害」に関連して会社が休業した場合には、たとえその休業が「会社の都合によらない休業」つまり会社に責任のない休業であったとしても、労働者は会社に対してその休業期間中の休業手当の支払いを請求することができるということになるのです。
「経営上の障害」によって生じる休業とは?
この点、具体的にどのような会社の休業が「経営上の障害」による休業に含まれるのかという点が問題となりますが、この点はケースバイケースで判断するしかありません。
もっとも、以下のような休業の場合には「経営上の障害」と判断することができると考えられていますので、以下のようなケースで休業が発生した場合には、たとえその休業に「会社の責めに帰すべき事由」がなかった、つまり「会社に休業に関する直接的な責任がなかった」としても労働者はその休業期間中の休業手当の支払いを請求することができるということになります。
労働基準法第26条の休業手当の請求が許容される「経営上の障害」に基づく休業の例
- 機械の検査(機械・設備の検査の実施によって会社が休業した場合)
- 原料の不足(原材料等の不足によって会社の操業が停止した場合)
- 流通機構の不円滑による資材入手難(たとえば交通渋滞による資材搬入の遅れで工場のラインが停止した場合、輸送船が故障して材料の搬入が遅れたなど)
- 監督官庁の勧告による操業停止(行政の臨検調査や勧告・処分等で操業が停止した場合など)
- 親会社の経営難のための資金・資材等の獲得困難
- その他
※出典:菅野和夫著「労働法(第8版)」弘文堂232頁を基に作成(※カッコ内は当サイトの管理人の注釈)
ですから、たとえばゴム手袋を製造しているA社が、原材料となる天然ゴムの輸送をB社委託している場合に、天然ゴムを積んだB社のトラックが運転を誤って事故を起こしたため原材料の搬送が遅れてしまい、A社の工場の製造ラインが停止して3日間休業が生じたというようなケースでは、A社に民法第536条2項の「責めに帰すべき事由」はないのでA社の工場に勤務する労働者はA社に対して民法第536条2項を根拠に休業期間中の「賃金」を請求することはできませんが、A社には労働基準法第26条の「責めに帰すべき事由」はあると判断されますので、A社の工場の労働者はA社に対してその休業期間中の「休業手当」の支払いを請求することができるということになります。
天災事変などの不可抗力によって休業が生じた場合は休業手当の請求はできないのが原則
なお、以上で説明したように、仮に「会社の都合によらない休業」であっても、その休業の原因が会社の「経営上の障害」に関するものである場合には、労働者は労働基準法第26条の規定を根拠にして会社に対してその休業期間中の休業手当の支払いを請求することができるということになります。
もっとも、これはあくまでも会社の都合によらない休業が「経営上の障害」と判断できる場合に限られますので、経営上の障害とは関係のない、たとえば天災事変などの不可抗力によって休業が生じたようなケースでは、労働者は労働基準法第26条を根拠にして会社に対して休業期間中の休業手当の支払いを請求することはできないのが原則です。
たとえば、地震や台風、土砂災害などの影響で会社の操業が停止し休業が発生した場合には、天災事変などの不可抗力によって休業が発生したということになりますので、その場合には労働基準法第26条の帰責事由は認められないものとして、労働者は会社に対してその休業期間中の賃金を請求することはできないということになるでしょう。
※ただし、豪雨や台風、地震等の天災事変など不可抗力によって生じた休業の場合であっても、「会社の施設や設備に直接的な被害が発生していない場合」には労働基準法第26条に基づいて会社に休業手当の支払いが義務付けられる場合もあります。
もっとも、以上にかかわらず、後述するように就業規則や個別の労働契約等で別段の定めがあればそれに従うことになります。
就業規則や労働協約、個別の雇用契約書(労働契約書)や労働条件通知書に別段の定めがあればそれに従う
なお、以上の考え方と結論はあくまでも労働法の通説や判例の解釈によって判断した場合の原則的な取り扱いになりますので、使用者と労働者の間で以上のような原則とは別に労働者に有利な取り扱いを労働契約の内容に規定している場合には、その労働契約の内容に従って解釈されることになります。
ですから、労働者が入社する際に会社から交付を受けた雇用契約書(労働契約書)や労働条件通知書、あるいは会社の就業規則や労働協約に
「会社都合によらない休業の場合にもその休業期間中の賃金の全額を支払う」
などと言った記載があれば、それが労働契約の内容となって契約当事者を拘束することになりますので、そのようなケースではたとえ「会社の都合によらない休業」の場合であっても労働者は会社に対してその休業期間中の賃金の「全額」を請求することができます(※ただし、この場合は民法第536条2項の規定を根拠に請求できるのではなく労働契約の根拠に基づいて請求できるということになります)。
また、仮に労働者が入社する際に会社から交付を受けた雇用契約書(労働契約書)や労働条件通知書、あるいは会社の就業規則や労働協約に
「会社都合によらない休業の場合にはその休業期間中の平均賃金の80%の休業手当を支払う」
という規定がある場合には、労働基準法第26条では「平均賃金の6割」と規定されていても、労働者は会社に対して「平均賃金の8割」の休業手当の支払いを請求できるということになります(※ただし、この場合は労働基準法第26条の規定を根拠に請求できるのではなく労働契約の根拠に基づいて請求できるということになります)。
また、仮に労働者が入社する際に会社から交付を受けた雇用契約書(労働契約書)や労働条件通知書、あるいは会社の就業規則や労働協約に
「天災事変などの不可抗力による休業の場合は平均賃金の6割の休業手当を支払う」
などと規定されている場合であれば、たとえ地震や台風等の不可抗力によって休業が発生した場合であっても労働者は会社に対して「平均賃金の6割」の「休業手当」の支払いを請求することができるということになります(※ただし、この場合も労働基準法第26条の規定を根拠に請求できるのではなく労働契約の根拠に基づいて請求できるということになります)。