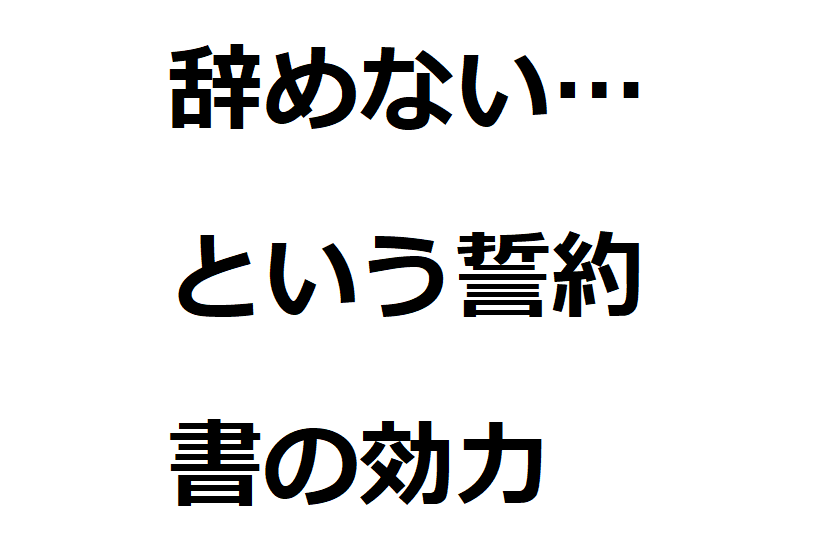稀に、雇い入れた従業員に対して「入社から〇年間は辞めません」とか「〇年〇月までは自らの意思で退職いたしません」などと記載された誓約書に無理やりサインを求めたり、その誓約書に署名しない限り入社を認めないとしている会社(個人事業主も含む)があるようです。
このような誓約書へのサインを求められた場合、労働者としては署名するのもしないのも自由ですから、もしその誓約書への署名が嫌だと思うのであれば署名を拒否して採用を辞退することも可能です。
しかし、仕事を探す労働者の側にしてみれば、せっかくもらった採用を無駄にしたくない気持ちが勝ることも往々にしてありますから、そのように会社側に迫られれば本意でなくてもその誓約書にサインせざるを得なくなるのが実情でしょう。
では、そのような誓約書に署名してしまった場合、その誓約書で誓約した期間が経過するまで自由に退職することができなくなってしまうのでしょうか?
「入社から〇年間は辞めません」「〇年〇月までは自らの意思で退職いたしません」などと記載された誓約書の有効性が問題となります。
「〇年まで辞めない」「〇年〇月まで退職しない」旨の誓約書は”基本的に”「無効」
結論から言うと、「入社から〇年間は辞めません」「〇年〇月までは自らの意思で退職いたしません」などと記載された誓約書は”基本的に”「無効」と考えて差し支えありません。
つまり、採用を受けた会社(個人事業主も含む)において、「入社から〇年間は辞めません」とか「〇年〇月までは自らの意思で退職いたしません」などと記載された誓約書にサインするよう求められ、かつ、その誓約書に自分の自由な意思で署名捺印していたとしても、「基本的には」その誓約書の存在は無視して退職届(退職願)を提出し、会社を辞めることができるということになります。
このような誓約書が「無効」と判断される理由はいくつかありますが、代表的な理由としては以下の(1)~(3)の3つが挙げられます。
(1)民法では「退職の自由」が認められている
このような誓約書が「無効」と判断される理由としてまず挙げられるのが、民法で「退職の自由」が明確に認められているという点です。
ア)期間の定めのない雇用契約(主に正社員)の場合
民法の第627条1項では「期間の定めのない雇用契約(※主に正社員など終身雇用)」の場合には「いつでも」解約の申入れをすることができるとされており、その解約の申入れを行った日から「2週間」が経過した時点(※解約の申入れをした日から2週間経過後に到来する日を退職日とした場合はその退職日が到来した時点)で雇用契約が無条件に終了するものと規定されています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
したがって、会社(個人事業主も含む)との間の雇用契約が「期間の定めのない雇用契約」である限り、退職届(退職願)を会社に提出して2週間が経過すれば、会社の承諾がなくても一方的に雇用契約を解除することが認められますから(※これが「退職の自由」ということです)、「入社から〇年間は辞めません」とか「〇年〇月までは自らの意思で退職いたしません」などと記載された誓約書にサインしていたとしても、そのような誓約書は無視して退職することができるということになります。
この点、誓約書に署名することでこの民法第627条1項で定められた「退職の自由」を「放棄した」と考える余地もないことはありませんが、この民法第627条1項の規定は法的には「強行法規」と解釈されており、この627条1項の規定に反して労働者の不利益になるような当事者間の合意を結ぶことは、たとえ労働者の合意があったとしても認められない(無効になる)ものと考えられています。
ですから、その面を考えたとしても、「入社から〇年間は辞めません」とか「〇年〇月までは自らの意思で退職いたしません」などと記載された誓約書の効力は「無効」と判断されますので、そのような誓約書は無視して、退職届(退職願)を提出することで好きな時期に仕事を辞めることができるということになります。
イ)期間の定めのある雇用契約(主にバイト・パート・契約社員)の場合
このような「退職の自由」は就労する期間を「いつからいつまで」と定めて雇い入れられる「期間の定めのある雇用契約(※主にパートやバイト、契約社員など)」の場合も同じです。
なぜなら、働く期間が一定の期間に定められて雇用される「期間の定めのある雇用契約」では、その契約時に合意した契約期間は退職できないのが原則ですが、民法の628条では「やむを得ない事由」がある場合、労働基準法の第137条でも「期間の初日から1年を経過した日以後」は契約期間の途中でも「直ちに」「いつでも」退職することが認められているからです。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
期間の定めのある労働契約(中略)を締結した労働者(中略)は、(中略)民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
(※注釈:ただし厚労大臣が定める高度な専門的知識を有する労働者や満60歳以上の労働者は適用除外されています)
この点、誓約書に署名することでこの民法628条や労働基準法137条に規定された「期間の定めのある雇用契約」における「退職の自由」を「放棄した」と考える余地もないことはありませんが、先ほどの「期間の定めのない雇用契約」の場合と同様、この民法第628条や労働基準法137条の規定も「強行法規」と解釈されていますので、これに反して労働者の不利益になるような当事者間の合意を結ぶことはできないものと考えられます。
したがって、「期間の定めのある雇用契約」の場合においても、たとえ誓約書で「入社から〇年間は辞めません」「〇年〇月までは自らの意思で退職いたしません」などと誓約していたとしても、「やむを得ない事由」があるか「契約期間の初日から1年が経過した後」であれば、そのような誓約書の存在は無視して退職することができる、ということになります。
(2)「強制労働の禁止」を規定した労働基準法の第5条が形骸化してしまう
「入社から〇年間は辞めません」「〇年〇月までは自らの意思で退職いたしません」などと記載された誓約書が”基本的に”「無効」と考えられる理由の2つ目は、そのような誓約書を有効と考えてしまうと「強制労働の禁止」を規定した労働基準法第5条の規定が形骸化してしまうからです。
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
この労働基準法の第5条は、憲法18条で規定された「奴隷的拘束の禁止」を具現化する法律となりますので、この労働基準法第5条も「強行法規」としてこれに反する労使間の合意は「無効」と判断されることになるのは当然です。
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
しかし、もし仮に「入社から〇年間は辞めません」とか「〇年〇月までは自らの意思で退職いたしません」などと記載された誓約書が有効とされてしまうと、この「強制労働の禁止」を規定した労働基準法第5条の存在が容易に無価値となってしまいます。
なぜなら、労働者が雇用主に雇われるという雇用契約(労働契約)は、形式体には労働者と使用者(雇い主)は契約当事者として対等(平等)であっても、実際には労働者よりも雇い主である会社(個人事業主も含む)の方が圧倒的にその力関係が上にありますから、使用者(雇い主)から「誓約書にサインしない限り雇わない」と言われれば、労働者としては誓約書への署名を拒否することは事実上困難だからです。
雇用契約を結ぶ場面では、仕事を求める労働者の方が圧倒的に弱い立場にあるわけですから、そのような誓約書の効力が有効と認められてしまうと、使用者(雇い主)はそういった「承諾書」を取ることで労働者をその「意思に反して労働を強制」させることが容易になってしまうでしょう。
そうなると、労働基準法第5条を定めた意味がそもそもなくなってしまいますし、ひいては憲法18条で禁止した奴隷的拘束も際限なく容認されることになってしまい不都合な結果となってしまいます。
「入社から〇年間は辞めません」とか「〇年〇月までは自らの意思で退職いたしません」などと記載された誓約書には、このような「強制労働の禁止」を形骸化してしまう問題が内在しているといえますので、その効力は「無効」と判断して差し支えないものと考えられるのです。
(3)憲法18条が禁止する「奴隷的拘束の禁止」や憲法22条が保障する「職業選択の自由」に反する
「○○までは辞めません」といった誓約書が無効と判断される理由の3つ目は、その誓約自体が憲法18条が禁止する「奴隷的拘束の禁止」や憲法22条が保障する「職業選択の自由」に反することになるという点です。
「奴隷的拘束の禁止」については前の(2)でも説明しましたが、そのような誓約書を有効としてしまうと「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」と規定した憲法18条が形骸化してしまい「奴隷的拘束の禁止」という重要な人権が何ら保障されなくなってしまいます。
また、憲法22条では「職業選択の自由」が保障されていますが、このような誓約書の効力を有効としてしまうと、使用者(雇い主)の恣意的な意思によって容易に労働者の「職業選択の自由」を制限することができることになってしまい不都合な結果となってしまうでしょう。
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
ですから、仮にそのような誓約書の効力が裁判で争われることになったとしても、憲法の規定に反する帰結が導き出されることになる結論を裁判官が採るとは考えられませんので、常識的に考えれば、そのような誓約書は「無効」と考えて差し支えないものと考えられます。
「〇年まで辞めません」「〇年〇月までは退職しません」という誓約書が「例外的に」有効と判断される可能性
以上のように、たとえ働き始める際に「〇年まで辞めません」とか「〇年〇月までは退職しません」といったような誓約書に署名捺印していたとしても、そのような誓約書の存在は無視して、退職届(退職願)を会社に提出し仕事を辞めることができるというのが原則的な考え方となります。
しかし、このような誓約書であっても特定のケースでは例外的に「有効」と判断される可能性も否定できません。
なぜなら、その「〇年まで辞めません」とか「〇年〇月までは退職しません」といった誓約書で誓約した「○○まで」という期間が「期間の定めのある雇用契約」における「契約期間」と判断される可能性もあるからです。
アルバイトやパートで雇われる場合には通常「〇年〇月から〇年〇月まで」というように一定の期間を定めた「期間の定めのある雇用契約」として雇い入れられるのが通常ですが、そういった明確な雇用期間を設定せずに、雇用条件をあいまいなままアルバイトを雇い入れている使用者も世間には多く存在しているのが実情です(※個人事業主や個人経営の会社で特に多いです)。
このような使用者(雇い主)では、「いつからいつまで」といったような明確な契約期間を示すことなく「じゃあ明日からすぐ来て!」といったあいまいな表現で雇用関係を結ぶこともしばしばみられますが、そのようなケースでは労使間で明確な「雇用期間」が設定されていないため「アルバイト」として雇われた場合であっても法律上は正社員で雇われるのと同じ「期間の定めのない雇用契約」で雇い入れられたものと推定されるのが原則です。
しかし、このような使用者(雇い主)に雇われたケースにおいて、「〇年まで辞めません」とか「〇年〇月までは退職しません」といった誓約書が存在していると、その誓約書に記載された「〇年〇月まで辞めない」とか「〇年〇月まで退職しない」といった文言自体が「期間の定めのある雇用契約」における「契約期間」にあたると判断される可能性も時としてありえます。
将来的に「辞める」「辞めさせない」で裁判になった場合には、裁判官はその雇用契約が「期間の定めのある雇用契約」であったのか「期間の定めのない雇用契約」であったのかをまず最初に判断しなければなりませんが、「期間の定めのない雇用契約」を示す契約書が存在していない以上、「〇年〇月まで辞めない」という誓約書が「期間の定めのある雇用契約」を内容とする契約書として有効か、という点をその他の事実認定によって判断しなければなりませんので、事実認定の如何によってはその誓約書が「期間の定めのある雇用契約」があったことを示す証拠として採用され、その誓約書に記載された「〇年〇月まで」は退職することができない(途中で辞める場合は契約違反になる)と判断される可能性もゼロではないのです。
もちろん、そのような誓約書にサインしたからといって、それが直ちに「期間の定めのある雇用契約」に関する契約書と判断されるものではありませんが、会社との間で「辞める辞めない」の問題が発生し、雇い主との間で結ばれた雇用契約が有期雇用契約か無期雇用契約か判然としないケースでは、「〇年まで辞めません」とか「〇年〇月までは退職しません」といった誓約書が「期間の定めのある雇用契約」が結ばれたことを示す証拠として裁判で採用されるケースも皆無ではないと考えられますので、その点は留意しておくことも必要と考えられます。
「○○まで辞めない」旨の誓約書を根拠に会社が辞めさせてくれないときの対処法
以上のように、たとえ働き始める際に「〇年まで辞めません」とか「〇年〇月までは退職しません」などと記載された誓約書に署名していたとしても、民法(627条または628条)や労働基準法(137条)の規定に従って自由に退職することが可能といえますので、大抵のケースではそのような誓約書は効力のないものと考えて無視しても差し支えないものと考えられます。
もっとも、そうは言っても誓約書にサインを求めた使用者(雇い主)側はそのような法律的な解釈を知らないがゆえに誓約書を取っているものと考えられますので、労働者の側がいくら上記で説明した正論を述べたとしても、誓約書の存在を根拠に退職の申し出を拒否したり退職を妨害してくることが予想されます。
そのような場合、次のような方法で具体的に対処するしかないかもしれません。
(ア)退職届(退職願)を会社に提出し退職の効力が生じた後は出社しないようにする
以上で説明した法律上の解釈を説明しても使用者(雇い主)が誓約書の存在を根拠に退職を認めない場合は、退職届(退職願)を会社(個人事業主も含む)に提出し、退職の効力が発生した後はいっさい会社に出社しないようにするしかありません。
先ほども述べたように、「期間の定めのない雇用契約」では退職届(退職願)を使用者(雇い主)に提出すれば、その日から「2週間が経過した日(※退職届の提出日から2週間経過後に到来する日を退職日とした場合はその退職日)」に退職の効力は有効に確定しますので、その「2週間が経過した日(※もしくは2週間経過後の退職日)」以降は一切仕事に行く必要はなくなるからです。
「期間の定めのある雇用契約」でも「やむを得ない事由がある場合」もしくは「契約期間の初日から1年が経過した後」は「直ちに」退職することができますから、「期間の定めのある雇用契約」で契約期間の途中で退職することができるケースでは、退職届(退職願)を提出して「直ちに(即日に)」退職し、それ以降は一切出社しなくても何ら問題ありません。
ですから、どうしても使用者(雇い主)側が誓約書の存在を根拠に退職を認めないような場合には、退職届(退職願)を提出し、その退職の効力が生じた後は一切出社しないようにするしかありませんし、それが最善の方法と言えます。
なお、この場合に提出する退職届(退職願)の記載例は以下のとおりです。
【退職届(退職願)の記載例】
株式会社○○
代表取締役○○ ○○ 殿
退職届
私は、一身上の都合により、△年△月△日をもって退職いたします。
以上
〇年〇月〇日
東京都〇区○○一丁目〇番〇号
○○ ○○ ㊞
(イ)退職届(退職願)を内容証明郵便で送付する
(ア)のような退職届(退職願)を会社に提出しても使用者(雇い主)側が退職を認めない云々と騒いでいる場合は、退職届(退職願)を内容証明郵便で送付しておいた方が良いかもしれません。
なぜなら、先ほども述べたように法律では「退職の自由」が認められていますので、(イ)の要領で退職届(退職願)を会社に提出すれば有効に退職の効力は生じますが、それでも使用者(雇い主)側が退職を認めないと主張するようなケースでは将来的に裁判等に発展する可能性も否定できないからです。
裁判になれば「退職届(退職願)を提出した」という事実の立証責任は労働者の側にありますが、単に手渡しで退職届(退職願)を提出しただけだと会社側が「退職届(退職願)など受け取っていない!」と主張してきた場合に、労働者の側が不利な状況に陥ってしまいます。
しかし、その場合であっても退職届(退職願)を内容証明郵便で送付しておけば会社が「受け取ってない!」と反論する場合であっても郵便局にその送付した証拠が保管されていますので裁判を有利に進めることが可能です。
ですから、会社側が誓約書の存在を根拠に執拗に退職を妨害しているようなケースでは、安全のために内容証明郵便を利用して退職届(退職願)を提出することも考えたほうがよいと思います。
なお、内容証明郵便で送付する場合の退職届(退職願)の記載例は以下のとおりです。
【内容証明郵便で送付する場合の退職届(退職願)の記載例】
退職届
私は、一身上の都合により、△年△月△日をもって退職いたします。
以上
○年○月○日
通知人
東京都〇区〇丁目〇番〇号
○○ ○○
被通知人
東京都〇区〇丁目〇番〇号
株式会社○○
代表取締役 ○○ ○○
(ウ)労働基準監督署に労基法違反の申告を行う
退職届(退職願)を提出しても、使用者(雇い主)側が誓約書の存在を根拠に退職を認めない場合には、ケースによっては労働基準監督署に労働基準法違反を理由とする申告を行うことも考えた方がよいかもしれません。
ただし、労働基準監督署は「労働基準法」という法律に違反した使用者(雇い主)に対してしか監督権限を行使できませんから(労働基準法第104条1項)、「○○まで辞めない」という誓約書の存在を根拠に使用者(雇い主)側が退職を認めないケースで労働基準監督署に労基法違反の申告ができるのも以下の「A」と「B]のケースに限られますので注意が必要です。
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
A)「暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」によって退職が妨害されている場合
「○○まで辞めない」という誓約書にサインしたことを理由に使用者(雇い主)が退職を認めない場合で、かつ「暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」によって退職を妨害され労働を強制されているようなケースでは、その使用者(雇い主)は労働基準法第5条に違反することになりますので、その旨を労働基準監督署に申告することによって監督署から調査や是正措置を取ってもらうことが期待できます。
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
ただし、「暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」を用いることなくに退職を妨害されているようなケースでは労働基準法5条違反とはならず、この労基法違反の申告はできないものと考えられますので注意が必要です。
B)「期間の定めのある雇用契約」において「契約期間の初日から1年が経過した後」に退職するケースで退職が妨害されている場合
先ほども説明したように「期間の定めのある雇用契約」では「契約期間の初日から1年が経過した後」であれば「やむを得ない事由」がない場合でも「いつでも」自由に退職することができます(労働基準法第137条)(※ただし厚労大臣が定める高度な専門的知識を有する労働者や満60歳以上の労働者は適用除外となっています)。
期間の定めのある労働契約(中略)を締結した労働者(中略)は、(中略)民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
したがって、「契約期間の初日から1年が経過」しているにもかかわらず使用者(雇い主)が「○○まで辞めない」という誓約書の存在を根拠に退職を妨害しているようなケースでは、その会社(個人事業主も含む)は労働基準法第137条に違反するということになりますので、「A」の場合と同様に労働基準法第104条1項に基づいて労働基準監督署に労基法違反の申告を行うことが可能といえます。
【注意点】
「期間の定めのある雇用契約」では「やむを得ない事由」がある場合も契約期間の途中で退職することが可能ですが、「やむを得ない事由」がある場合の退職を認めているのは民法の628条になりますので、使用者(雇い主)が「やむを得ない事由」の存在を否定して退職を拒否しても労働基準法違反にはなりませんから、民法の628条を根拠として「やむを得ない事由がある」という理由で契約期間の途中で退職しようとしている状況において使用者(雇い主)が「○○まで辞めない」という誓約書の存在を根拠に退職を認めないケースでは、労働基準監督署に労基法違反の申告を行うことができませんので注意が必要です。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
(エ)以上の対応でも退職を妨害される場合
以上で説明した(ア)(イ)(ウ)の対処を行っても使用者(雇い主)が「○○まで辞めない」という誓約書の存在を根拠に退職を認めない結果としてトラブルが継続している場合には、労働局に対して「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいた「助言や指導」を求めたり「あっせん」の申請を行って紛争解決委員会による「あっせん」の手続きを利用することも考える必要があります。
また、全国の弁護士会や司法書士会が主催しているADR(裁判外紛争解決手続き)を利用して弁護士や司法書士の同席の下で会社側と退職の可否を話し合いを行ったり、弁護士や司法書士に個別に相談し示談交渉や裁判を行ってもらうことでトラブルを解決することもケースによっては検討する必要性があるといえます。
なお、これらの対処法を取る場合の具体的な相談場所等についてはこちらのページにまとめていますので参考にしてください。